- TOP
- 共同利用完遂記念 座談会 〜岡山天体物理観測所が果たした役割とこれから〜

岡山天体物理観測所の開所から「すばる望遠鏡」の建設へ
進行話題を次に移しましょうか。次は前原さんが所長を務められていた時代ということで、すばる望遠鏡の建設計画が進む中で岡山天体物理観測所がどのように変わってきたかというお話をお聞きしたいです。あとは東京天文台が国立天文台という組織に変わった時期なので、そのあたりのお話も。
前原私、実は今日がこの岡山の観測所の終わりというか、閉めるとかということ(注:共同利用観測所としての終了)に絡んだ座談会ということで、何となく抵抗を感じていまして。事実はそうだとしても、この際だから、少し夜明けの開所のころの岡山観測所のある種、雰囲気かもしれない、事実だと思いますけれども、そういうところをこの機会に紹介させてほしい。
進行それもぜひ。
前原つまり、その時代は皆さん、本当に張り切っていて。先ほど沖田さんが言ったけれども、彼はまだ何年かたってから就職しているけれども、最初のころの人たちは私、随分長くつき合ってきたが、亡くなった人もいるけれども、皆さんすごくある種の志と言っていいのかな。そういうものを持っていたと思います。ここの観測所がいかに重要か。自分がそこでいかにきちんと仕事をしていくかということを真面目に、本気でやっていましたね。そういうことを最初に紹介させてほしい。
それで言うと、岡山天体物理観測所40周年記念誌の最初のほうに書いてある、萩原雄祐博士の直訴事件というもの、御存じですか。
進行私は記念誌で読んだきりなので、それ以上のことは。
前原これは非常にすごいことだった。これは個人プレーではあるのですけれども、萩原先生、私のいた最後のころには東大のほうに帰ってこられて、もちろん定年されて随分経っていらしたけれど、「みんな元気?」という感じで教室に出て来られた。
そのときはもう好々爺だったのですけれども、これをされたころはすごかったらしいです。東京天文台の台長と東大の教授をやっていて、日本の天文学をこれからどうしようかということに非常に真剣に取り組んでいた。その1つの証拠がここにありますけれどもね。どうやって岡山ができたかということの1つのエピソードですけれども。新年の講書始めというものがあり、いろいろな分野の教授とかプロが招かれ、御進講申し上げるわけですが、1953年の正月はたまたま彼がその役の一人を仰せつかって、そのときに彼は既にもう意識していたわけです。その前の年に世界に行ってきて、1953年ですから、終戦から10年たっていない時期です。日本がまだまだ経済発展する前のことですけれども、日本はこのままではとても天文学は立ちおくれてしまってどうしようもない。何とか大きな望遠鏡が欲しいとね。天体物理学というものの大事さというものを身にしみて感じて、講書始めでの天文学の講義の最後に、ここに文章で書かれていることをされた。後で直していただくといいのだけれども。
進行はい。引用を入れておきます。
萩原雄祐博士の直訴事件
1953年の正月である。「たまたま新年の講書始めの進講者の一人に私(萩原雄祐博士)が選ばれた。その日は早朝に目がさめた。進講の原稿に望遠鏡のことを書き足した時の私の心境は実に澄みきっていた。昔ならば直訴ははりつけの刑をうける!佐倉宗五郎を思いうかべて、次の時代のために生命を賭ける喜びに震えていた。天体の進化について進講申しあげた後で。こんな研究をするには大望遠鏡が必要である。1億5千万位あればできるのでそれが欲しいと申し上げた。聴講の人たちの間にはざわめきが起っていた。しかし私は総理大臣の吉田(茂)さんが欠席されていたのは返えす返えすも残念であった。吉良を打ち損じた浅野の心境であった。聴講の学者たちは文部大臣の大達さんに、あんなに云っているのだから買ってやれと云ってくれたらしい。別室で御馳走になっていた我々進講者のところへ宮内府長官がきて話してくれた。しかし私は内心穏かではない。直訴は死刑である。私はその足で大学へ行って矢内原総長に私はこうこうの悪いことをしたから応分の御処分をといった。矢内原さんは笑って答えない。それから文部省に行って稲田局長にも、こうこうのことをしたから大学総長にいって私を処分させてくれと話したが、これも笑って答えない。進講をきいていた岡野さんは先生よかったですよと云う。その後は何の音沙汰もなく、次の時代のために生命を投げ出した甲斐があってここに74吋の望遠鏡ができあがったのである。」
これは、天文月報第54巻(1961年)に書かれた「直訴事件」の真相である。
前原こういうことをやるために今、日本には適当な望遠鏡なり装置がない。これをぜひ私は欲しいと思っている。金額まで言ったらしいです。1億5,000万円。それだけのお金があれば、そういうものが買えて、それで新しい日本の観測天文学ができるようになりますということをその場で、もちろん、ほかにも聴講者はいたらしいですけれども、申し上げた。彼は、もうこんなことを言ってはいけないと思っていることを言ったもので、当時の台長職も賭して、それをやめる覚悟で言ったのです。
年を取ってから聞いたら、うん、まあ何とかと言って、軽くしか説明してくれなかったけれども、これが本当だと思うのです。この数ページ後に沿革とありますけれども、その同じ年の1953年の5月には、学術会議からもう大望遠鏡の設置を政府に要求しているわけです。それから半年もたたない時期です。だから、そのことがすごく大きなきっかけになっている。
学術会議もすぐ動いてくれて、そういう動きになった。その後どういうことが起こったかというと、もう翌年に望遠鏡の予算措置。
進行国の予算可決というのが記念誌に載っています。
前原あるでしょう。予算を可決して、それで調査を開始する。今、普通こんなに早くないでしょう。
沖田たいていもっとかかりますね。
前原だから、萩原さんの一撃というか、サッカーで言えば一蹴りというかね。それがすごい影響があったということがこの結果を見るとわかる。
建物工事が1958年から始まっているわけでしょう。当然どこにするかという試験観測がその間に入っていますから、もうこれ以上短くならないぐらいの時間間隔ですね。それで1960年に開設ですからね。調整して立ち上げて。とても速くスムーズに進行したということに、40周年記念誌を作ったときにすごいなと思ったのです。それは萩原さんをたたえるというよりは、そのときの萩原先生や周りの人たちの、そういう気持ちが非常に強かったのだなという証だと思います。
それでとんとん拍子に始まった。それが岡山天体物理観測所ですね。注文した望遠鏡は何台目かですけれども、望遠鏡も、グラブ・パーソンズという本当のプロの製作会社が請け負っていいものを作ってくれた。それをここへ設置した。それが1960年で、その後2年ぐらい、テスト観測やら何やらやって1962年から実質的な共同利用が始まったわけですからね。全国を対象に。当時は海外とまでは言わなかったかもしれない。最初から10年経たない間に本格運用まで行ってしまっているのです。これはぜひこの機会に言わせてほしいと思ったのです。
それもあってここはそういうものが今でも脈々と生きているのだろうな。私がここへ職員として来て所長をやっているときも、どこかに感じていましたね。こんなに57年たってもまだ。あの当時からやめるとか閉めるとか、いっぱい出ていたけれども、きちんとそれなりにその時代に合わせながら続いてきたということなのです。
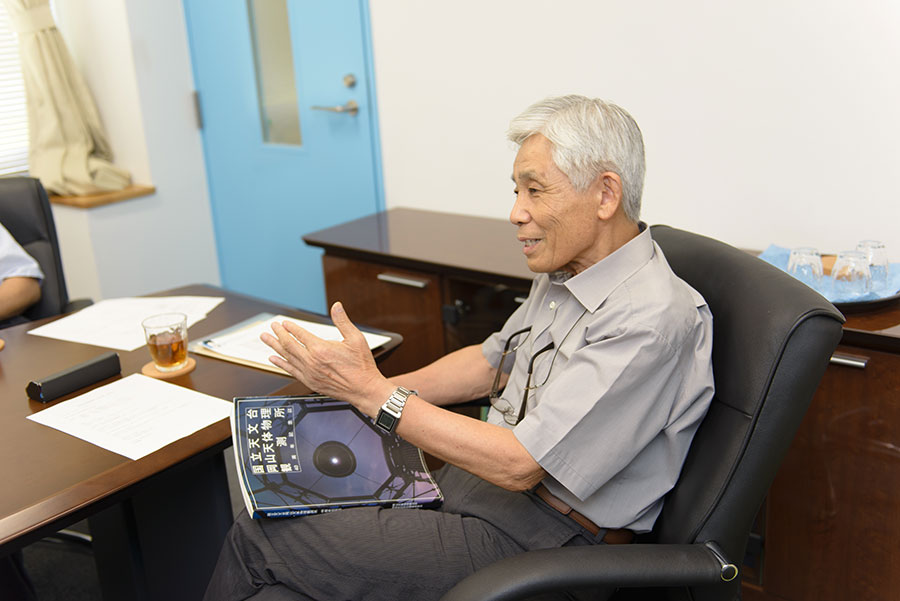
前原もう一つ、それに絡んで言うと、ここはこんなに良い場所ですから、当然、当時の経済発展で光害が起こる。それに対して私も所長時代にそれなりに一生懸命動きましたけれども、県や地元の行政関係、市町村はかなり協力してくれました(1972年:岡山天体物理観測所観測協力連絡会議結成)。理想的なほど暗くないけれども、ある程度のところで結構長い間保っている。そういうものが岡山観測所の基本の大きな礎にあるのだなというのは感じていたのです。その第3代の所長を私は拝命して、何とか務めていたのです。
結局、その1962年から始まった実質的共同利用でどんどん新しい研究者が生まれて、若手が育って、世界にもちゃんと出せるような結果、研究成果を出している。でも、そうしているうちに当然、混んでくるわけです。最初から10年ぐらいはそんなではなかったのですけれども、以降はどんどん人がふえて、しかも暗い天体をやりたいとか、新しい装置を使いたいとか、そういう要求が強くなって、私がここに職員として来るころに、皆さんが言っていたのは、共倒れ。
つまり、やりたい人が多くて、それをプログラムに組みますね。観測プログラム、「すばる」だって同じですけれども、そのころは一番極端な場合は二晩、三晩ということもあって、低気圧が来て曇れば、ただ来て帰るだけというようなことが起こってきた。それはよくないということで、1988年の改組を機に、そこを改善しようということで改革をした。
それが共同利用の実質的な部分で、レフェリー制※を敷いた。最初はレフェリーというと当時の人たちはすごい拒否反応を示したので、スクリーニング制と言い換えたけれども、要するにレフェリー制です。プログラム小委員会をつくって、レフェリーの評価を参考にしながら観測プログラムを決めていこうということから始めて、私はそのころに矢面に立たされていました。とにかく、そういう時代でした。
スクリーニング制(レフェリー制)
1989年後期より、岡山天体物理観測所の観測プログラムにスクリーニング制が導入される。岡山188cm望遠鏡の共同利用の変遷 スクリーニング制とプロジェクト制(岡山天体物理観測所40周年記念誌p.49)
スクリーニング制(レフェリー制)導入についての議論(岡山天体物理観測所40周年記念誌p.195)
前原私がここへ来て少したったころにもう「すばる望遠鏡」(当時は「大型光学赤外線望遠鏡, JNLT(Japan National Large Telescope)」と呼ばれていた。)という話がどんどん出始めて、1990年になって「すばる望遠鏡」の本格的な建設が始まるわけです。その期間は10年近くありますけれども、建設している間はまだ観測はできないわけですから、その間に国としての日本の天体物理学をシフトしていかなければいけないということになります。建設をするためにはお金も要るけれども、人が必要で、しかも、新人を連れてくるのでは役に立たない。だから「すばる望遠鏡」建設チームから見ると一番即戦力になる人というのでね。そもそも野口猛さん(岡山観測所から木曽観測所経由ですばるへ)、彼がここの最初の技術者だったのだけれども、彼はいろいろな仕事をしながら次々に沖田君もそうだし、もっと若手の浦口君だとか。
泉浦湯谷さんもいました。
前原湯谷さんもいた。そうだね。まだいるね。倉上さんもいる。死んだ子を数えるようなものですけれども、岡山から見るとすごくしんどい時代でしたね。その上で共同利用も進めていかなければいけない。予算もまだ全然回ってこなくて、むしろこちら側から出せという感じで。それでやっていったら、新しいものなどは何もできない。そういう中で私は悪戦苦闘して、でも、とにかくちゃんと「すばる望遠鏡」をつくって、それがスムーズに動かなければいけないから、一所懸命やってみたのです。
そのときの苦しさだけを今、訴えたみたいだけれども。「すばる望遠鏡」が完成した後で岡山をどうするかという話ね。それを私なりには随分真剣に考えた。岡山会議とか勝手に名前をつけて、台長の海部さんも引っ張り込んで、それと関係者で。あれはきちんと任命してではなくて、これと思う人に来てもらって、ワーワー議論したのです。その結果、岡山はもちろん閉めたりする方向へ行くのはよくないから、じゃあ何でやっていこうかというときに、当然望遠鏡は変わらないわけで、これからいいサイエンスができるような装置をつくろうではないかということになった。
いろいろなタイプの装置がありますけれども、ある程度汎用性があって、新しいことに挑戦できるような装置をつくろうという議論が主になった。それで最初に、OASISという日本で初めて本格的な近赤外の観測装置。山下卓也さんがPI(Principal Investigator、主任研究員)で、何年か来てもらったのです。それで若手が3人こちらに来て。それは「すばる望遠鏡」とは少し前にずれるかな。
沖田「すばる望遠鏡」の建設期間中です。
前原大体その期間。
泉浦シューメーカー・レビーは1994年。
前原忘れかけていたけれども、1994年に大体できた。でもまだカバーが無く、これからテスト観測しなければいけないというときに起こった天文イベントがシューメーカー・レビー第9彗星の木星衝突です。あれは夏でしたね。
進行記念誌には7月と書いてありますね。

シューメーカー・レビー第9彗星の木星衝突(1994年)、OASISの華々しいデビュー
前原OASISが使えるのではないかと、渡部潤一君たちもやってきて、みんなで。ちょうどそのころはメッキをして、整備期間だったのですけれども、その整備期間をそういうことに使ってみようというので、91センチのほうも関係者が来て、188センチのほうはOASISで近赤外でやってみた。ふだんの観測は特にメディアに知らせないですけれども、たまたまこの天文のイベントはメディアが関心を示して、東京あたりの大きな新聞とかテレビがこぞって来た。ここに詰められても困るからと、遙照山にできたばかりの企業の保養所があって、そこの好意で、会見場にしようということになった。とにかく私も自分の日常的な業務はありましたけれども、結局会見をさせられて、私、初めてテレビに映りました。7時のニュースにシューメーカー・レビー彗星が木星に衝突しましたと。天文のイベントでもあのくらいビッグになるとNHKの7時のニュースでも取り上げるのですね(注:岡山に関連したものとして、2015年1月4日NHK総合午後7時のニュースの中の記事「”第2の地球探し”ことし本格化」で188cm望遠鏡と多色撮像装置MuSCATが紹介、2015年12月15日NHK総合ニュースウォッチ9で国際天文学連合(IAU)主導の系外惑星命名キャンペーンName Exo Worldsの結果の紹介などがある)。とにかく我々としては、ある意味報われたというか。それだけ社会に知られたら私たちがやっているということがわかるわけですから。地元の人からもニュースを見ましたよ、あなたたちも仕事をしているのだなと言われたのです。夜な夜な何かやっているらしいけれども、天文台は何をやっているのだろうと思っている地元の人もいらしたのでしょう。そんなイベントがいつもあるわけではないけれども、それはある意味、私にとっては非常によかったですね。それが1994年。40周年記念誌を作ったおかげで、まだ記憶に残っているのです。
沖田40周年でもう本当に終わるという意識が結構あったのかもしれないけれども、前原さんのときに立派に作ってあるのです。いろいろな人の寄稿文を載せてあるのだけれども、50周年のときは同じものを載せるのではなくて、その後のいろいろな成果が何かというのを中心に全部載せたのです。
前原50周年は50周年で必要です。
泉浦50周年記念誌、台長からそんなに立派なものは作らないようにと言われましたよね。
沖田そうです。私が言ったら、そんなもの出さなくていいでしょうとか言うから少し薄くしました。40周年記念誌と50周年記念誌を合わせると観測所の歴史が非常によくわかるような。だから、片方ではだめというようにつくったのです。戸田君にものすごく大変だと言われながら。
進行CDをつけて、40周年記念誌をCDに収録して、それを付録にして、50周年記念誌と両方合わせて50年分の記念誌ですよと。
沖田これが全部入っている。
進行今は、この2冊と今回のウェブ版で57年誌というか、岡山天体物理観測所誌という感じでまとめようと考えています。
岡山天体物理観測所の歴代記念誌はPDFでダウンロードすることができます。
記念誌ダウンロード
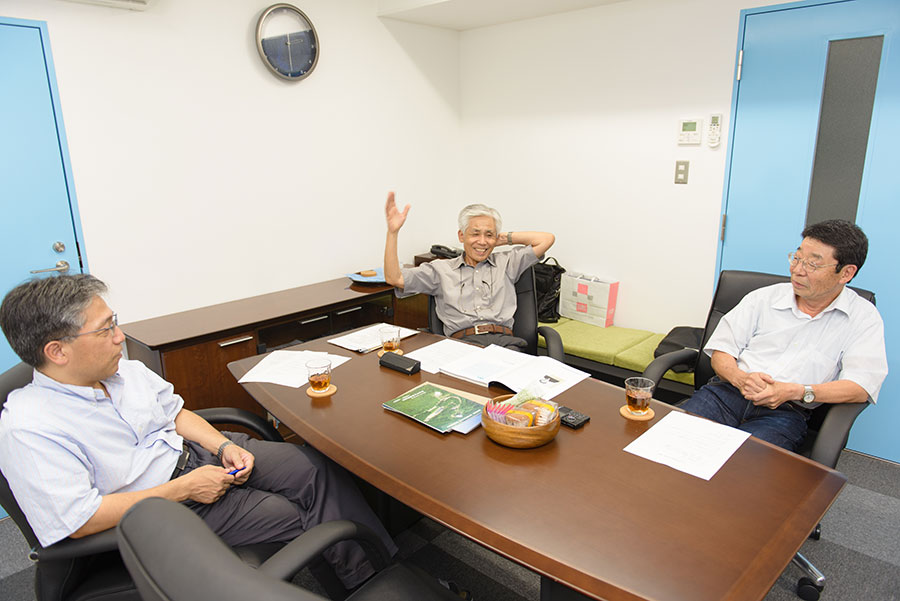
進行ちなみに前原さんがいらっしゃる間に、岡山天文博物館のプラネタリウムもできたということですが。
前原そうですね。1988年に改組がありましたけれども、それと連動するようにして博物館のほうも改組した。
泉浦県立から変わったのですか。
前原そうです。博物館にとってみればかなり大ごとだったのかな。
沖田観測所運営委員会と県の中に何かありましたね。
前原私も委員だったけれども。
沖田そこが運営しているという形だったのだよね。
前原今で言うと、最初から第三セクターに近かった。
進行県立とは全然名乗っていませんでしたね。
沖田だから、県も名前だけ貸しているという感じ。
前原でも、人件費は県から出ていた。
沖田あそこで働いている人たちの人件費は県が出してくれていた。
前原そうですね。寄り合って、観測所のほうも運営に関与している。地元の当時は3町、まだ合併していなかったので、鴨方町と金光町と矢掛町。1960年から1988年で二十何年間運用されてきて、プラネタリウムなどはなかったのですけれども、そういう形で運用されてきたのを改組に連動して、大西さんという当時の鴨方町長が、自分のところで引き受けようと。うちがやりますと言って県から移管して、望遠鏡とプラネタリウムは県からの資金で購入した。浅口市になった時は田主さん。鴨方町と金光町と、寄島町も含めて、浅口市になった。全部似た時期に起こっていて、岡山天文博物館が浅口市立になって、プラネタリウムと太陽望遠鏡もその時作って、新しい体制で運用を始めた。ちょうど天文台も改組になったし。
1つの時代が終わって新しい時代になったのですけれども、そこから先の話は先ほど言ったようにかなりイバラの道がありました。でも、すばる望遠鏡の建設ということで正しい方向というか、日本にとっていいことはわかっていたので。「すばる望遠鏡」が21世紀に変わるころにでき上がって運用が始まることになって、私も2001年の3月31日60歳で定年になったのですけれども、それがほとんど時期的に合っているのです。
沖田2001年だった。私、2002年にこちらにまた戻ってきた。だから、本当に1年ぐらいしか一緒にいなかった。避けていたのかもしれないけれどもね。

