
何事もなくプロジェクトが進む。これ、事務の仕事です
事務部 総務課 給与係 係員
栢森 真司
Shinji Kayamori
三鷹、水沢、野辺山、ハワイ、チリ。守備範囲は広め
国立天文台の事務部には総務、財務、経理、施設、研究推進の5つの課があります。拠点としてはここ三鷹のほかに水沢(岩手県)、野辺山(長野県)、ハワイ、チリがあり、その5課5拠点の範囲で2年ないし4年スパンに異動をします。私も最初の4年間は経理課調達係で契約の仕事をやっていました。その後、総務課に移って人事を。今は同じ総務課ですが給与係に替わって俸給の決定、各種手当の認定、給与に係る税業務などを行なっています。それなので年末調整のある年末や年度末・年度始めは忙しくて残業も増えます。逆に6月から8月は比較的に落ち着いていて、それから秋の気配とともにひたひたと年末がやってきて……、という感じでしょうか(笑)。
出張もあります。ない年もありますが、多いと年に2回ぐらいは。ほかの拠点に内部監査に行ったり、プロジェクトからお声がけいただいて水沢と野辺山の特別公開(注)のお手伝いに行ったり。またIAU(国際天文学連合)の総会が3年に1度開かれるんですけれど、2018年にウィーンで開かれた時はそちらへも行きました。
それから経理課にいたころ、年度末の金曜日に突然上司に「お前、パスポート切れていないか?」と聞かれて、1週間後の週末にはチリへ出発していたなんてことも。会計業務の手伝いで事務所とホテルを行き来するだけの毎日だったんですが、現地の研究者の方が見かねたのか、ご飯に連れて行ってくれて。あれは嬉しかったです。
- (注)国立天文台の施設で年に一度、行われるイベント。通常の施設見学とは違い、普段見られない観測・実験装置が公開されたり、研究紹介や天文学者による最新の研究成果の講演、地域との協力イベントなどが行われます。水沢、野辺山では例年、8月に行っています。

正直、社会に出ることにビビっていたんですよ
私が国立天文台に入ったのは2014年の8月です。2013年に大学院を修了してから就職はせず、バイトでつないでいました。無理に就職する必要もないという考えもあったりして。その状態で1年たって“そろそろ就職するか”となったときに、国立天文台で働けるらしいというのを知って、採用試験(国立大学法人等職員採用試験)を受けることにしました。もともと三鷹(の国立天文台)に見学に来たり、高校生の時にハワイのヒロにホームステイしていてすばる望遠鏡のことを知っていたり、それで国立天文台だったら働きたいと思って。5月に筆記試験、6・7月に面接、で合格して8月から出勤し始めたという経緯です。
正直に言うと、就職するまでは縦のしばりとかがきついんじゃないかと、社会に出ることにビビっていたんですよ。でもそのビビりは通勤し始めて数日で解消されました(笑)。皆さん優しくて、先生たちも気さくで。
入って3カ月後ぐらいのことですが、特別公開の打ち上げで「偏屈な方とか、嫌なことを言われることもある」みたいなことを私が言っていたら、ある先生が「がんばって仕事をしているのを認めている人がいるのに、一部の人の言葉で腐るのはばかばかしいよ」とおっしゃったのは印象に残りました。
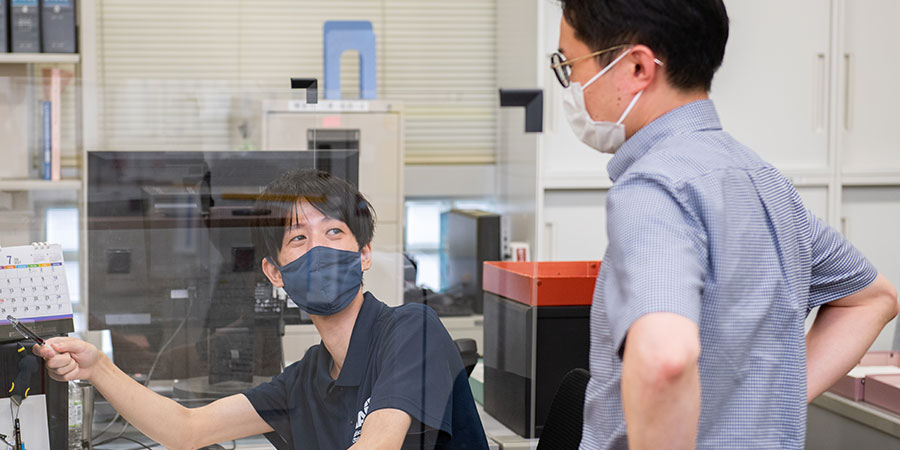
“この人について行こう”と、そのとき思いました
いまでも忘れられないのは、国立天文台に入って半年ぐらいのときに調達の仕事をしていて、契約にかかわることで大きなミスを犯したんです。気付いた時にはもう取り消しが効かない状況で、国立天文台のプロジェクトにも、発注先の業者さんにも迷惑をかけることになってしまい……。それを知った上司が一緒に、プロジェクトの方のところへ「監督不行き届きで」と謝りに行ってくれたんです。でその後、私に対しては「見ていなくてごめんね」って。……もう頭が上がりませんよ。“この人について行こう!”と、そのとき思いましたね。
小さなミスは今でもやはりどうしても発生してしまうのですが、それを指摘してくれるとき、この職場では個人を責めるようなことはないです。そのミスが生まれた環境とか、要因を考えてくれたりするのが先輩たちや上司ですね。
また別の話ですが、繁忙期、仕事中に具合が悪くなって休養室で寝ていたら、お昼に先輩とか上司が「お粥とかなら食べられるかなー?」って、お昼ご飯を買って持って来てくれたこともありました。自分の体調管理がなっていなかったせいで、忙しい中、穴をあけてしまったのに。「ここは天国か」と思いましたよ(笑)。

資質よりも“自分が仕事とどう向き合うのか”が重要
国立天文台の事務職って、こう、ぼやーっとした状態の課題があって、それを整理してインデックスをつけて、規定規則や法律に合うよう処理する、そんなイメージです。法令や規則にのっとることは当然で、曲げてはかえってその人のためにならないのですが、でもそこで大切なのは、どんな仕事の向こう側にも人がいて、その人の顔を想像できるということ。法令・規則のラインを守りつつ、その課題の背景にいる人の身になって考えることができる。そういった当事者意識が求められる仕事だと、私は感じています。 そして“何事もないことこそがやりがい”ということも。ミスがない、当たり前の状態をいかに維持できるか、最近はここにやりがいを感じるようになってきました。
私なんて中学生のころはあまり学校に行っていませんでしたし、大学院修了した時は就職なんかしなくてもいいと考えていた。子供の時から『銀河鉄道の夜』が好きで何度も読みましたが、天文への関心なんてそれくらいで、科学的な知識はほとんどありませんでした。それでも今、適職につけていると思います。
組織って1種類の人間だけではダメなんじゃないですかね。コミュニケーション能力の高い人、コツコツと丁寧に作業に集中できる人、いろいろな人が集まっているべきだと。苦手なものが1つ2つあったとしても、得意なことで十分に能力を発揮できればいい。さらに言うと、資質よりも“自分が仕事とどう向き合うのか”の方が重要なのかもしれません。

取材日:2021年7月12日/公開日:2021年9月17日
取材・文:臼田雅美/写真:長山省吾
掲載内容は取材時のもの