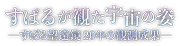TOPIC 02
すばる高解像度観測能力の進化 ―惑星形成、系外惑星、重力レンズ―
補償光学装置(AO)を備えたすばる望遠鏡は、高解像赤外線観測に威力を発揮し、若い星の周りに広がる、惑星の元となるガス雲―原始惑星系円盤―の研究に活躍した。AOにコロナグラフ撮像装置CIAOの組み合わせは、若い恒星AB Aur(ぎょしゃ座AB星)の周囲に原始惑星系円盤が渦を巻いて分布している様子を明らかにした。これは原始惑星系円盤撮像の先駆的な観測成果である。
- [ウェブリリース]すばるが写し出した、うずまき状の惑星誕生現場
- [参考文献]Fukagawa et al. 2004, ApJ Letters, 605, L53, “Spiral Structure in the Circumstellar Disk around AB Aurigae”

さらには、若い連星系の原始惑星系円盤の詳細構造を見ることにも成功し、理論計算との詳しい比較から、惑星形成過程での外部からの物質供給の様子を世界で初めて明らかにした。
- [ウェブリリース]すばる望遠鏡、双子の若い星の星周円盤を直接観測 ―星周円盤に外部からの物質流入を初めて検出―
- [参考文献]Mayama et al. 2009, Science, 327, 306, “Direct Imaging of Bridged Twin Protoplanetary Disks in a Young Multiple Star”

すばる望遠鏡の高解像度観測路線は、さらに進化したコロナグラフ撮像装置HiCIAOの登場によって、新たな展開を迎え、ついに太陽系外惑星を直接撮像することに成功した。太陽型恒星GJ 504の周囲を巡るGJ 504bは、それまで直接撮像された太陽系外惑星の中で最も暗く温度が低いもので、「第二の木星」と言って良い。
- [ウェブリリース]すばる望遠鏡 SEEDS プロジェクト、「第二の木星」の直接撮影に成功
- [参考文献]Kuzuhara et al. 2013, ApJ, 774, 11, “Direct Imaging of a Cold Jovian Exoplanet in Orbit around the Sun-like Star GJ 504”

すばる望遠鏡の補償光学システムはさらに進化し、レーザーガイド星による大気揺らぎ補正が実現した。レーザーガイド星を用いると、大気揺らぎ補正に使える明るい星が無い天域でも、AO観測ができる。この機能により、重力レンズ効果を受けたクエーサー像の観測を行い、重力レンズを起こしている銀河を検出することに成功した。レーザーガイド星AOはその後も銀河などの高解像度観測において活躍している。
- [ウェブリリース]レーザーガイド星補償光学での遠宇宙観測が本格始動~ 10 倍になった視力で初めてみえた重力レンズ銀河 ~
- [参考文献]Rusu et al., 2011, ApJ, 738, 30, “SDSS J133401.39+331534.3: A New Subarcsecond Gravitationally Lensed Quasar”