- イベント
第23回 自然科学研究機構シンポジウム 「現代天文学のフロンティア―第二の地球とダークな宇宙」
お知らせ
YouTube(録画あり) ニコニコ生放送(タイムシフトあり)
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構は、天文学、核融合科学、分子科学、生物学、医学生理学などを柱として、分野を超えた融合研究を積極的に行い、自然科学の新しい分野の開拓を進めています。このような分野を超えた自然科学研究の意義を多くの皆さんにお伝えすることを目的に、「自然科学研究機構シンポジウム」を開催してきました。
第23回目となる今回は、天文学分野に焦点をあて、現代天文学の挑戦的な2つのテーマ―太陽系外惑星とダークマター―を採り上げます。国際協力の下、天文学的・素粒子物理的な手法で迫る宇宙の謎と最新の研究成果について、研究者自らが解説する講演会です。
概要
- テーマ
- 現代天文学のフロンティア―第二の地球とダークな宇宙
- 日時
- 2017年3月5日(日曜日)午後1時から午後4時50分(開場 正午)
- 会場
- 東京国際交流館(プラザ平成) 国際交流会議場(東京都江東区青海2-2-1 国際研究交流大学村内)
アクセス - 定員
- 360名、事前申込制(先着順)
参加のお申し込みはウェブサイトから受け付けます。 参加申し込み - 参加費
- 無料
- 主催
- 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構
プログラム
- 12:00
- 開場
- 13:00-13:10
- 開会挨拶
小森 彰夫(自然科学研究機構 機構長)
林 正彦(自然科学研究機構 理事/国立天文台 台長) - 13:10-13:50
- 講演1:太陽系外地球型惑星を見つけよう
林 左絵子(自然科学研究機構 国立天文台 ハワイ観測所 准教授) - 13:50-14:30
- 講演2:系外惑星誕生の現場を見つけよう
武藤 恭之(工学院大学 教育推進機構 基礎・教養教育部門 准教授) - 14:30-14:40
- 質疑応答(講演1、2について)
- 14:40-15:00
- 休憩
- 15:00-15:40
- 講演3:広視野天体探査で調べるダークマターの分布
宮崎 聡(自然科学研究機構 国立天文台 先端技術センター 准教授) - 15:40-16:20
- 講演4:ダークマターの正体を探れ ―地上実験による直接探索―
末原 大幹(九州大学 理学研究院物理学部門/先端素粒子物理研究センター 助教) - 16:20-16:30
- 質疑応答(講演3、4について)
- 16:30-16:45
- まとめ
- 16:45-16:50
- 閉会挨拶
竹入康彦(自然科学研究機構 副機構長/核融合科学研究所 所長)
講演内容
講演1:太陽系外地球型惑星を見つけよう
地球のような惑星はこの宇宙のどこにあるのでしょう。太陽系の中でも地球に似た資源を持つ環境の探査が進められ、また太陽ではない別の恒星をめぐる惑星の観測も急速に進展しています。続々と見つかる太陽系外惑星候補の中には、その温度環境から水が存在できるかもしれないものもあります。地球や太陽系の成り立ちを理解する上で、他の惑星系から得られる知見は貴重なものです。本講演を通じて、すばる望遠鏡で進められている研究の努力とわくわくを皆さんと分かち合いたいと思います。
林 左絵子(はやし さえこ)

自然科学研究機構国立天文台および総合研究大学院大学 物理科学研究科天文科学専攻准教授。電波天文学により理学博士号取得。秋田県生まれ、福島を含む東北育ち。イギリス・オランダ・カナダ連合天文台勤務の後、国立天文台に入り、すばる望遠鏡の設計段階から携わる。1998年よりハワイ勤務。大型電波望遠鏡のパラボラ鏡面調整による効率向上、大型光学赤外線望遠鏡の基本光学系やコーティングに携わってきた。研究テーマはミリ波・サブミリ波観測により分子雲中における星形成活動や、赤外線観測により星・惑星系形成過程を目撃すること。
講演2:系外惑星誕生の現場を見つけよう
惑星は、生まれたての若い星の周りにある「原始惑星系円盤」の中で誕生したと考えられています。原始惑星系円盤の中にある大きさ1マイクロメートルにも満たない塵(ちり)が、100万年以上の時間をかけて惑星にまで成長していきます。人間から見ると長いように見える100万年も、星や惑星の生きる時間に比べるとほんの一瞬です。すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡などで、この一瞬を捉えようとする試みが行われています。本講演では、最新の観測で明らかになってきた惑星誕生の現場についての理解をご紹介します。
武藤 恭之(むとう たかゆき)
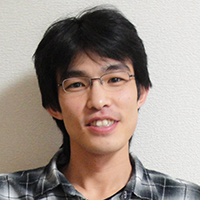
工学院大学教育推進機構基礎・教養教育部門 准教授。博士(理学)。惑星形成過程に関する理論的研究を中心に、観測的な研究も行っている。京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻修了。日本学術振興会特別研究員、工学院大学助教を経て、2015年より現職。2015年、日本惑星科学会最優秀研究者賞を受賞。
講演3:広視野天体探査で調べるダークマターの分布
かつては次第に減速していくものと考えられていた宇宙膨張。しかし、1990年代後半、宇宙膨張が加速しているという観測的な証拠が見つかり、大問題になりました。このこの発見者には、2011年のノーベル物理学賞が授与されました。我々のグループは、この宇宙膨張の問題の真相に迫るため大型の超広視野カメラを開発しました。すばる望遠鏡とこの最新のカメラを組み合わせて宇宙のダークマター(暗黒物質)の分布を調査することで、宇宙膨張加速の謎の解明に迫ります。
宮崎 聡(みやざき さとし)
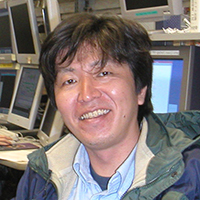
国立天文台 准教授。理学博士。1993年東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了。1994年ハワイ大学天文学研究所(日本学術振興会海外特別研究員)を経て、1996年より国立天文台に勤務。主な研究分野は観測的宇宙論、観測装置開発。
講演4:ダークマターの正体を探れ ―地上実験による直接探索―
ダークマター(暗黒物質)の存在は宇宙の最大の謎の一つであり、素粒子実験においてもこのダークマターを手がかりに、既存の理論の枠組みを超えたまったく新しい理論が発見できるのではないかと、注目を集めています。大規模な装置と国際的な協力の下、さまざまなアプローチで進められるダークマター探索実験をいくつかご紹介するとともに、特に次世代大型加速器計画として日本への建設が有望視されている国際リニアコライダー(ILC)によるダークマター探索についてお話しします。
末原 大幹(すえはら たいかん)
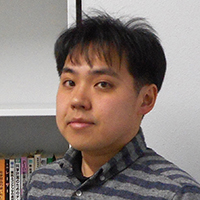
九州大学理学研究院物理学部門・先端素粒子物理研究センター 助教。博士(理学)。国際リニアコライダー(ILC)の加速器、測定器、物理解析を渡り歩き、ILCの実現に邁進するとともに、大強度陽子加速器施設(J-PARC、茨城県東海村)、高エネルギー加速器研究機構(KEK、茨城県つくば市)、福井大学などの装置を使った中小規模の新物理探索実験も行っている。2008年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。その後、東京大学素粒子物理国際研究センター特任研究員、東北大学大学院理学研究科助教を経て2013年より現職。
講演要旨集ダウンロード
参加申し込み
受付終了
定員に達したので参加申し込みを締め切りました。
お問い合わせ
自然科学研究機構 国立天文台内 自然科学研究機構シンポジウム担当
電話:0422-34-3600(代表、平日8:30-17:15)
電子メール:sympo23@nins.jp
