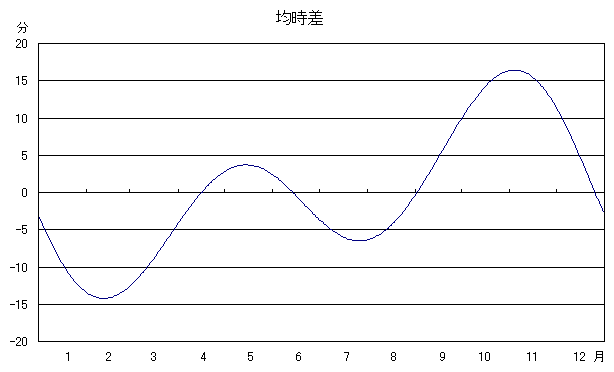質問1-7
太陽の南中時刻は日によって変わるの?
太陽は星座を形づくる星々の間を東へ東へと1日に約1度移動し、1年で星座の間を一回りします。(本当は地球が太陽のまわりを回っているのですが、地球から観察すると、太陽が星々の間を動いているように見えます。)この、東に向かって移動する速さが1年中まったく変化しなければ、南中時刻は毎日同じ時刻になることでしょう。しかし実際には、太陽の移動する速さはわずかですが変動していて、速く動く時期と遅く動く時期があるために、南中時刻も日によって変わることになります。
もし、太陽が南中する時刻が毎日同じ時刻になるように1日の長さを決めてしまうと、ある時期の1日は24時間を超えていたり、またある時期の1日は24時間より短かったりしてしまいます。そこで私たちは、太陽の速さの変動をならしてしまった平均の長さを「1日の長さ」と定義して使っているのです。(天文学では、実際に見えている太陽とは別に、いつでも同じ速さで移動する仮想の太陽を考え、これを「平均太陽」と呼んでいます。これに対して、実際に見えている太陽のことは「視太陽」と呼びます。)
それでは、なぜ太陽の東に移動する速さが変化するのでしょうか。それには大きく2つの理由があります。
- 地球が太陽のまわりを回る軌道が完全な円ではなく楕円のため、太陽に近いときには速く動き、太陽から遠いときには動きが遅くなります。そのために、地球から見た太陽の動きの速さも、それにしたがって変動します。
- 太陽は、夏には北寄りに移動し、冬には南寄りに移動します。(このために季節の変化が生ずるのです。地球が太陽のまわりを回る平面を基準にして、地球の回転軸が傾いていることが原因です。)太陽が動く速さが一定だったとしても、この南北への移動が大きいとき(春分・秋分前後)にはその分東への移動量は小さくなり、南北への移動が小さいとき(夏至・冬至前後)には東への移動量が大きくなります。
「視太陽」と「平均太陽」との位置の差を時間に換算したものを「均時差」と呼びます。毎日の均時差の値は、国立天文台が編纂する「理科年表」などに書かれています。均時差の値がプラスの場合には南中時刻が平均より早く、値がマイナスの場合には南中時刻が平均より遅いことを意味します。(ただし、本によっては均時差の値の定義がプラス・マイナス逆になっていることがありますので、ご注意ください。)