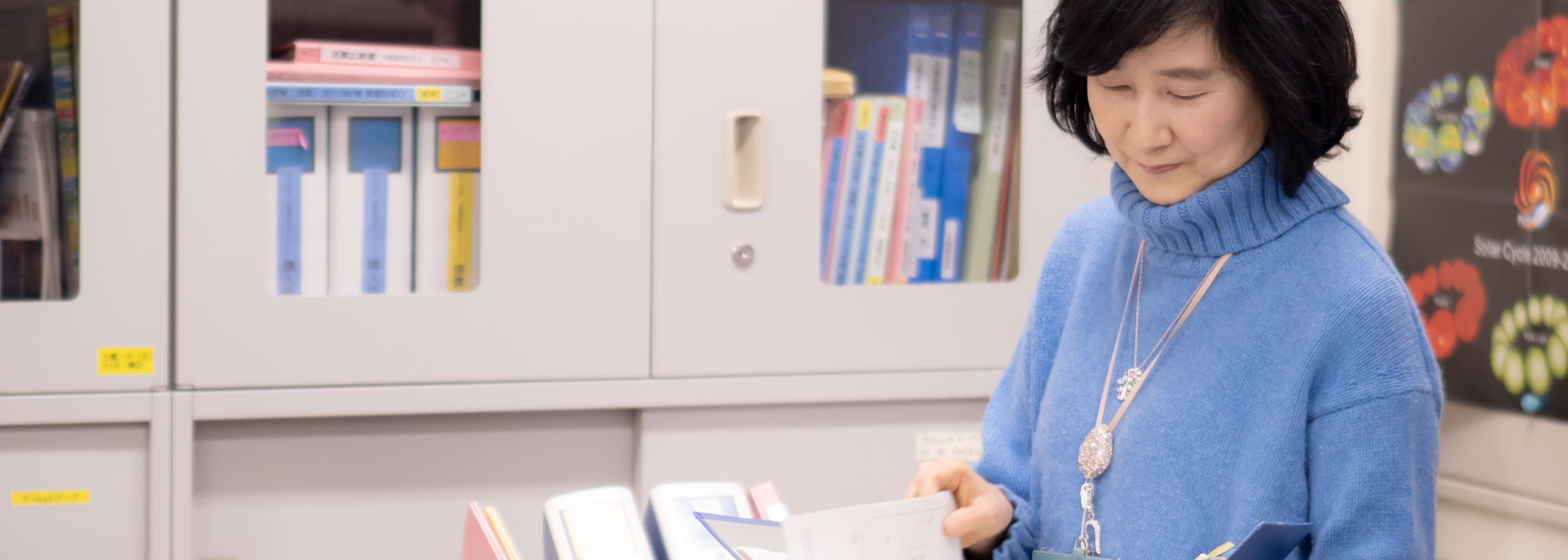
事務の仕事に誇りがもてる、そんな環境と人々
SOLAR-Cプロジェクト 事務支援員
杉本 順子
Junko Sugimoto
今年はSUNRISE-3の国内での作業が大詰めで……
私の仕事はSOLAR-Cプロジェクト専属の事務で、ネジなどの部品・材料・器材の発注や海外輸送等の手続き、研究者の出張の旅費申請・総務業務などを主にやっています。国立天文台で行う太陽関係の研究会や国際会議の手伝いもあり、海外からの参加者を案内するときなどは、英語で会話することも必要になります。日頃のメールなどのやり取りでも海外との連絡はとりますが、こちらは間に研究者が入ってくれたり、翻訳機能もあるので、それほど英語力が必要というわけでもないですね。
今年度はちょうどSUNRISE-3の国内での作業を完成させて、出来上がったものをドイツへ送るというタイミングで、それまでより多くの仕事量があって。新しい業者さんとのやりとりなどが、ちょっと大変でした。輸出に向けて保険の手配も必要で、滞りなくできたか、いざとなったときに保険がおりなかったらどうしようとか、緊張してやっていました。この仕事に専門的な知識は必要ないと思いますが、チームの皆さんのサポートをする役割なので、協調性というか、いろいろな方と仲良くやれる性格の方が向いているかなと思います。
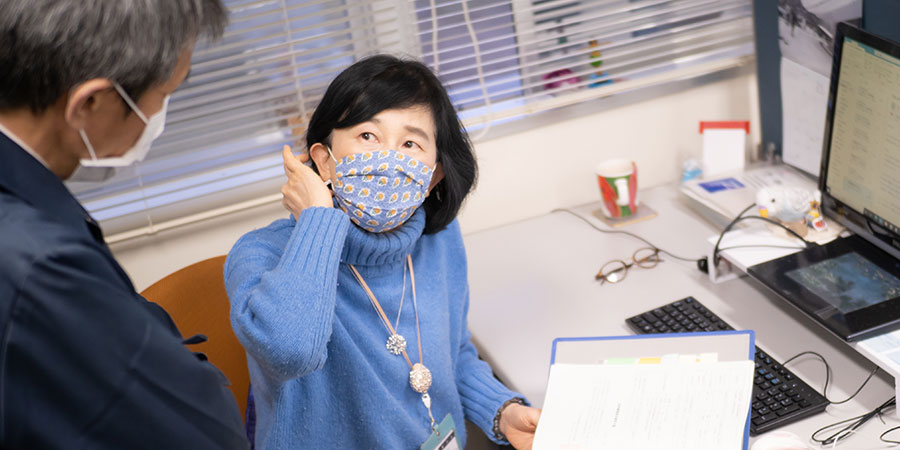
この人たちの役に立てるのは、私の誇りです
私は1993年に国立天文台に事務補助員として入って、3年で退職した後、一度ほかの研究所へ行ったんですね。それからまた2006年に国立天文台に戻ってきて、太陽観測所の事務支援員に。2020年度から担当がSOLAR-Cプロジェクトになったんですが、このプロジェクトはとても熱いものを感じるというか……。先日、『サイエンスZERO』という番組で国立天文台の話をやったんですが、それを見て初めて皆さん、本当にすごいことをやっているんだなぁって。なんだか怖くなりましたねぇ。研究者の方々がとても熱く語っていて。この人たちのすぐ下で、私、ネジとか買っているんだぁって(笑)。天文という専門性の高いものに関わって、最先端をいっている人たち、頑張っている人たちを見ることができる、サポートできるというのは、誇りかなと思います。そんな皆さんがつつがなく動けるように、これからもお手伝いしていきたいです。

分け隔てなく、尊重してくれる環境
これは私のプロジェクトだけでなく、国立天文台全体で言える話だと思うんですけど、非常勤だから、事務だからといった差別が全然ないんです。研究者の人たちって分け隔てがないと言うか。コツコツやっていればそれぞれを尊重してもらえる。見ている人は見ていると感じます。私がここに入ったばかりの頃、大きな会議があって、遅くまで残業していたとき、いつもは近寄りがたい雰囲気の教授がメールの最後に「おつかれさま」って。そのときはキュンと胸にくるものがありましたね。大変な思いをしても、苦労を忘れます。
それからある日気づいたことがあって……、私たち事務の者が朝、事務室に出勤すると、エアコンのスイッチがいつもすでに入っているんです。それは後から分かったんですが、もっと早く出勤している研究者の方が、私たちが寒い思いや暑い思いをしないようにと、こちらの部屋のエアコンもスイッチを入れてくれていたんです。そういったさりげない気遣いって本当にうれしいですよね。

仕事だけじゃない、こころのゆとりが
以前、同じ事務の先輩に「あそこにお花植えませんか?」って言われて、玄関の前の花壇に花を植え始めたんです。その先輩はもう退職されて、今は私ひとりで育てているんですけど。いつも少し離れた場所から水をくんできて水やりをしていたら、ある日、花壇のすぐ横の水道が自由に使えるようになっていて。どなたかが栓をつけてくださったんですね。また世話をしていると、いろいろな方が声をかけてくれるのも、励みになります。
国立天文台はクラブ活動が盛んで……。私は2018年に合唱部を立ち上げたメンバーの一人なんですが、最初は3、4人だったのが、多い時は20人ぐらいまで。今はコロナの影響で活動を休止しているんですけど、皆さん練習に来ると本当に楽しそうな表情をなさるんですよ。歌で仲間とつながる夢が叶いました。それから折り紙クラブにも私、入っていて。(机上に飾ってある作品を指して)このヨーダなんか、雰囲気出ているでしょ(笑)?
国立天文台にはほかにもサッカー部とか野球部とかいろいろあって。研究室に来ている学生さんたちも一緒にそこで汗を流して、また研究に没頭する……。仕事だけじゃない、そういう心のゆとりが、国立天文台の雰囲気にも表れているんじゃないでしょうか。

2021年2月26日/公開日:2021年4月15日/最終更新日:2021年4月19日
取材・文:臼田雅美/写真:飯島裕
掲載内容は取材時のもの