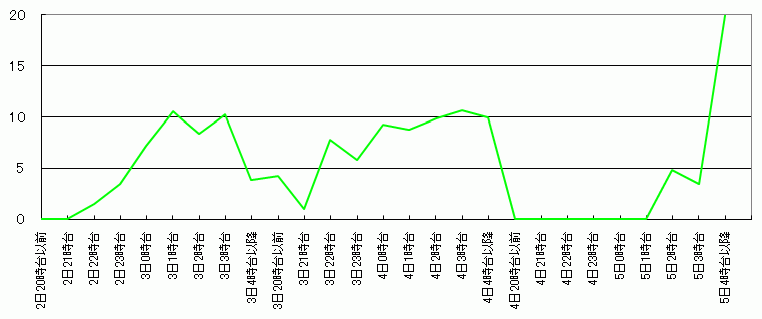
グラフのデータ
観察日時ごとに、観察された流星の数を、1時間あたりの流星数におおまかに換算してグラフにしました。
今回のキャンペーンでは、流星群の活動が変化する様子は、あまりはっきりとはグラフに現れていないようです。
※ 正確な流星の個数・観察時間・雲の量・空の暗さなどはご報告いただいておりませんし、流星の出現数は放射点の高度によっても違います。その他にもいろいろ不確定な要素がありますので、ここで算出した流星数や変動の傾向が、現実をそのまま表しているかどうかは確かではありません。
5日4時台以降の流星数が大きな数値を示していますが、流星群が実際に活発な活動を示したわけではないと思われます。4日から5日にかけての夜は報告数がたいへん少ない(10人以下)ため、少数の極端なデータが数値に大きな影響を与えてしまったようです。
2日から3日にかけての夜にも、その次の夜と同程度の活動をしたように見えますが、これも、実際の流星群の活動を表したものではないと思われます。3日から4日にかけての夜の報告が始まるまでは前夜の流星数はもっと小さな値でした。それが、3日から4日にかけての夜の報告が始まると、値が増加していったのです。想像になりますが、3日から4日にかけての夜の報告を、日付を間違え、前夜の日付で報告してしまったものが混ざってしまっているのではないでしょうか。(データからは確認のしようがありませんが。)
日本流星研究会の速報集計によると、今年のしぶんぎ座流星群では、4日2時台から4時台に1時間あたり約40〜50個、5時台には1 時間あたり約70個の流星が観測されています。
IMO(国際流星機構:英文)の報告によると、世界的には1月3日の22時前後に極大が訪れたようです。日本ではこのころ、放射点がまだ地平線の下にあるか大変低い位置にありましたので、流星はほとんど出現しなかったと考えられます。その後、真夜中を過ぎた頃からは日本でも放射点が徐々に高くなり、極大を過ぎた流星群の活動を目にすることができました。もしも極大が、ちょうど日本での観察に適した時刻に訪れていたとしたら、もっと多くの流星が見られたのでしょう。
※ 時刻はすべて日本時間です。
※ 「群流星だけを観察した」報告をピックアップし、「天候が悪い」を外して集計しました。例えば、流星数は「3〜5個」を「4個」、観察時間は「11〜20分」を「15分」などとして計算をおこないました。