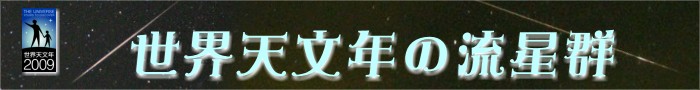
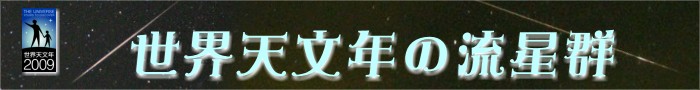
このページでは、三大流星群を除く、その他の流星群を解説いたします。これらの流星群の中には、出現する流星数は少ないものの毎年見られる流星群や、例年はあまり流れないのに、年によっては三大流星群をしのぐ流星数が観察される流星群などが含まれます。
4月22日頃に極大を迎える流星群です。普段の年の流星数はそれほど多くありませんが、ときおり突発的に流星数が増加することがあります。国内では1945年に1時間あたり約90個の記録があり、海外では1922年、1946年、1982年などに流星数の増加が観測されています。
2009年の極大は、4月22日14時〜20時頃になりますが、こと座の放射点が空高くなってくる4月22日23時頃から翌朝までがおすすめの観察時間帯でしょう。月明かりの影響がないため、その点では好条件で観察することができます。
母天体は1861年に出現し、太陽の回りを約400年で公転するサッチャー彗星(Thatcher彗星)です。ただし、彗星の公転周期と突発出現の周期はあまり関係がないようです。
5月の連休の頃に極大を迎えるのが、このみずがめ座η(イータ、エータとも表記される)流星群です。母天体は、10月のオリオン座流星群と同じで、有名なハレー彗星(1P/Halley)です。みずがめ座に放射点のある流星群は7月にもありますので(みずがめ座δ流星群)、放射点近くにある恒星の名前「η(イータ)」を必ず付けて、区別して呼ばれます。
この流星群は、放射点の位置の関係で北半球の中・高緯度での観測は難しく、日本では明け方の1時間くらいしか見ることができません。一方で南半球では、三大流星群のペルセウス座流星群に匹敵するほどの流星数が観察されることがあります。
極大は5月6日頃ですが、それほどはっきりしていません。前後数日間は同じくらいの流星が観測でき、また1日の中では深夜2時頃から夜が白み始める3時半頃という短時間が、観察のチャンスです。
7月中旬から8月中旬まで、長い期間活動するのが、このやぎ座α流星群です。ゆっくりと流れるのが特徴で、見られる流星の数はさほど多くありませんが、火球と呼ばれるような明るい流星が流れ、目をひきます。
極大は7月29日頃とされますが、ほとんどはっきりせず、前後一週間くらい見ごろが続きます。月が早めに沈む7月下旬のうちに観察するのが良いでしょう。なお、この流星群は、ほぼ一晩中観察することができますが、放射点の高い真夜中前後の数時間が、より好条件となります。
やぎ座α流星群とほぼ同じ時期に活動するのが、このみずがめ座δ(デルタ)流星群です。5月のみずがめ座η流星群と区別するために「δ(デルタ)」を必ず付けて呼ばれます。
やぎ座α流星群と比較すると、やや速く流れ、また明るい流星はあまり多くないようです。ただし、放射点の位置は近いため、初心者が区別するのは難しいかもしれません。
観察は、月が早い時間帯に沈む7月下旬のうちが観測に適しています。ほぼ一晩中観察できますが、放射点が少し高くなる23時頃からより好条件となります。
なおこの流星群は、北群と南群に分けられる場合もありますが、現在は、南群だけがほぼ観察されており、この南群だけを「みずがめ座δ(デルタ)流星群」と呼ぶことが多いです。
通常は、お盆が過ぎた頃から流れ出すのが、このはくちょう座κ(カッパ)流星群です。流星が流れる最後の末端で爆発することが多いとも言われています。
放射点は、一晩中地平線の上にありますが、明け方に沈みかけますので、夕方から2時頃までが観察に適しています。極大と言われる8月20日前後は、月明かりの影響も受けませんので、観察しやすいでしょう。
流星数はさほど多くないのですが、ときおり明るい流星が増加したり、活発な時期が早まったりするので、注意が必要です。近年では2007年に、お盆前から明るい流星が増えて注目されました(ただし、別の流星群の活動だった可能性も考えられます)。今年はどうなるでしょうか。
約6.5年の周期で太陽を公転しているジャコビニ・ジンナー彗星(21P/Giacobini-Zinner)が母天体の流星群です。日本では、一般的にジャコビニ流星群という名前が通っていますが、世界的にはりゅう座流星群とも呼ばれます。
この流星群は、母天体が2公転する13年ごとに出現のチャンスがあり、1933年にヨーロッパで、1946年にはアメリカで流星嵐が観察されました。しかし、日本で好条件と思われた1972年はさっぱり流れなかったという苦々しい経験があります。
その後日本では、1985年と1998年に1時間あたり100個程度の活発な出現が観察されました。
このような年以外では、ほとんど流れないのですが、近年は熟練の観測者を中心に、1時間に数個程度の流星が毎年観測されています。2009年も少々の出現があるかもしれませんが、数が少ないと思われるので、あまりおすすめはできません。
ダスト・トレイルの解析では、2011年10月8日深夜〜9日未明に大出現が予報されていますが、残念ながら、日本では放射点が低い時間帯となり悪条件です。
10月中旬から下旬にかけて流れるのが、このオリオン座流星群です。みずがめ座η(イータ)流星群とともに、母天体がハレー彗星(1P/Halley)であることが知られています。
これまでは、熟練者が観察しても1時間あたり20個を超えることはあまり無かったのですが、2006年に突然1時間あたり60個以上、観測者によっては100個を超える流星数が観察され、にわかに注目されています。これは、ダスト・トレイル理論の研究により、およそ3000年前にハレー彗星から放出された塵によって流星数が増加したものだと報告されています。なおこの研究によれば、塵は2006年〜2010年頃で接近傾向にあり、2009年もやや活発な流星出現が観察される可能性があります。
極大は、これまで10月21日頃とされてきましたが、2006年の大出現では3〜4日間も活発な出現が続き驚かされました。この傾向は2009年も続いていると考えられ、10月19日頃から25日頃まで目が離せない状況です。
ちなみに流星は22時頃から流れ始めますが、放射点が高くなる0時過ぎから本格的に流れるでしょう。極大付近は月明かりの影響もありませんので、日付は10月21日をはさんだ数日間、時間帯は深夜0時頃から明け方までが観察におすすめです。はたして、流星がどのくらい見られるのか、ぜひ注目してみましょう。
11月上旬を中心に、10月末から11月中旬くらいまで流れるのが、このおうし座流星群です。火球と呼ばれる明るい流星が多く流れ、偶然目にすることも多い流星群のようです。放射点が南と北に分かれていて、それぞれ南群、北群と呼ばれています。
極大は、南群の方が早く11月5日頃、それから約一週間遅れて北群が11月12日頃とされますが、ゆるやかな極大なので、11月前半を通して、この流星群を目にするチャンスがあるでしょう。
流星は夕方から一晩中流れますが、放射点が高くなる21時以降が好条件です。2009年の場合、11月の早い時期は月明かりの影響を受けますが、日が経つにつれて月の出が遅くなるので、11月7日頃以降で、月が上る夜半頃より前の時間帯が好条件でしょう。
母天体は、太陽の回りを約3.3年で公転するエンケ彗星(2P/Encke)と言われます。しかし、現在流星群を形成している塵は、かなり古い時期に放出されているようで、彗星の接近と流星数の増加は無関係のようです。なお、火球が増加する年については研究報告があり、残念ながら2009年は普通ですが、この先2012年や2015年頃に火球が増えると予想されます。
しし座流星群は、過去に多くの流星嵐が記録されていることで、大変有名な流星群です。母天体はテンペル・タットル彗星(55P/Tempel-Tuttle)で、この彗星の公転周期である約33年ごとに流星嵐のチャンスがあるとされてきました。過去には1799年、1833年、1866年、1966年などに激しい流星嵐が観察されています。
2001年11月18日深夜〜19日未明には、日本でも1時間あたり1000個を超える流星が見られ、流星嵐となったことは記憶に新しいところです。一方で、2003年以降は、流星数がかなり少なくなっています。
しし座流星群は、ダスト・トレイル理論と呼ばれる流星群の新しい予報手法が適用され、その理論の確立に一役買ったことでも知られます。2001年の日本での流星嵐を含め、1999年から2002年に見られた流星嵐や流星数の増加は、ほぼ予報通りに起きています。
この手法による予報では、1400〜1500年代に放出された塵が作るダスト・トレイルが、2009年11月18日の未明〜午前中にかけて接近することが判明しています。極大は、日本の夜明け後となってしまう可能性が高いのですが、もしかしたら空が白み始める頃に、流星数が増えるのが観察できるかもしれません。月明かりの影響も全くありませんので、11月17日深夜から18日の明け方まで、注目してみましょう。
一年のしめくくりとなる流星群が、こぐま座β(ベータ)流星群です。12月22日頃の極大前後数日間に、流星が見られます。
例年は流星数が少ないこぐま座流星群ですが、ときおり流星出現が活発化します。過去には、1945年や1986年に流星数が増加しており、また1981年には、数はさほどではありませんでしたが、明るい火球が多く流れているのが確認されました。
放射点は北極星に近く、一晩中観測できますが、深夜0時以降の方が放射点の高さが高くなりおすすめです。2009年のこぐま座流星群は、12月22日22時半頃に極大を迎えるとされており、月もちょうど22時頃に沈みますので、12月22日22時頃から23日の明け方にかけてが、観察におすすめの時間帯となります。
母天体は、太陽の回りを約14年の周期で公転するタットル彗星(8P/Tuttle)です。現在、この母天体からの塵についてダスト・トレイル理論を適用した予報が、盛んに研究されており、過去の活発な出現の検証や、これからの予報が試みられています。残念ながら、今のところ2009年にこのこぐま座流星群が活発化するという情報はありませんが、より古くに放出された塵が計算されると、新たな予報が発表されるかもしれません。