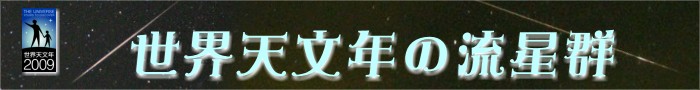
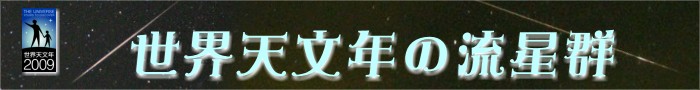
毎年ほぼ安定して、多くの流星が流れる3つの流星群「しぶんぎ座流星群」「ペルセウス座流星群」「ふたご座流星群」は、「三大流星群」と呼ばれます。
このページでは、この「三大流星群」について、解説いたします。
一年の最初を飾る流星群が、しぶんぎ座流星群です。三大流星群のひとつとして数えられますが、流星の出現数は年によってかなりムラがあり、どのくらい流れるか予想するのが難しい流星群でもあります。
このため、熟練の観測者によって1時間あたり100個程度見られた年も、時々ありますが、通常は1時間あたり20個から50個程度です。
なお「しぶんぎ(四分儀)座」という星座は、ありません。これは、放射点のある辺りにかつて「壁面四分儀座」という星座があったことに由来しています。また「りゅう座ι(イオタ)流星群」と呼ばれることがありますが、正式には「しぶんぎ座流星群」が用いられます。
しぶんぎ座流星群は、1月に入った頃から流れ始めますが、数が比較的多く観察されるのは、極大の前後1日程度です。また、際だって流星数が増加するいわゆる極大は、数時間しか続きません。
その極大は諸説あるのですが、2009年の場合、1月3日夜から4日未明(3日深夜)までの時間帯となります。日本国内で多く観測される極大は、1月4日未明(3日深夜)3時半頃となり、日本では好条件で観察できるものと期待されます。しかし、極大は、ずれる可能性もあり、実際には観測してみないとわからないでしょう。
しぶんぎ座流星群の放射点は、うしかい座とりゅう座の境界付近にあります。放射点が上ってくる深夜0時頃から流星は流れ始めますが、本格的に流れるのは3時以降です。その後は、明け方6時頃に空が白み始めるまで、観測することができます。
極大の条件を考慮すると、1月4日未明(3日深夜)2時〜5時くらいに観察するのがおすすめです。ただし、流星数が少ないことも考えられます。
極大の頃の月は上弦ですが、夜半前の23時頃に沈みますので、流星群は月明かりの影響を受けずに観測することができます。好条件と言えるでしょう。
母天体は諸説あり、まだ確定的ではありません。2003年に発見された、小惑星番号 196256 の小惑星(仮符号 2003 EH1)が、近年では有力視されています。ただし、この小惑星が、どのように流星の元となる塵(ダスト)を放出したのかは、わかっていません。
このほか、1490年に一度だけ出現した1490 Y1 という彗星や、マックホルツ彗星(96P/Machholz)も母天体の候補としてあげられています。まだまだ不明な点が多い流星群のひとつです。
国立天文台では、月明かりの影響を受けず、また極大(の一説)の時間帯が観測できるこのしぶんぎ座流星群を多くの人に見てもらうために、「見えるかな年の初めの流星群」キャンペーンを行います。
1月2日の夜から5日の朝までの3夜の間に15分間以上星空 を眺め、結果を報告ページから報告していただこうというものです。世界天文年のスタートを切る天文現象ですので、ぜひみなさんもご参加ください。
三大流星群のひとつで、年間でも常に1・2を争う流星数を誇ります。条件がよい時に熟練の観測者が見ると、1時間あたり60個以上の流星が観測されます。極大の時期がお盆の直前なので、夏休みなどの時期と重なり多くの人が注目しやすい流星群です。
ペルセウス座流星群は、7月の下旬には流星が流れ始めると言われています。ただし流星数が増えるのは8月の中旬になってからです。
2009年の極大は、8月13日未明(8月12日深夜)の2時30分頃と予想され、日本で観測しやすい時間帯にあたります。その点では好条件と言えます。
ペルセウス座にある放射点は、夕方には地平線の上にあり流星が出現する可能性があります。しかし、実際に流星を目にし始めるのは、もう少し放射点が高くなる21〜22時頃となります。さらに、本格的に流れ始めるのは0時を回ってからです。明け方まで放射点は高くなり続けるので、空が白み始めるまで観察しやすい時間帯が続きます。
極大時刻も考慮すると、8月13日未明(12日深夜)の0時〜4時頃の観察がおすすめです。しかし、前日と翌日の同じ時間帯にも、ある程度の流星数が期待できるでしょう。
極大の頃は、下弦の月が夜半前に上ってきます。ちょうど流星が流れ始める頃と重なるため、月明かりの影響を受けてしまい、残念ながら暗い流星は見づらくなるでしょう。
母天体は、スイフト・タットル彗星(109P/Swift-Tuttle)です。太陽のまわりを約130年かけて回っています。
2009年には、1862年に放出されたダスト(塵)が作るダスト・トレイルと地球が接近することが判明しています。8月12日14時頃なので、日本では全く観察できませんが、ヨーロッパ等では流星数の増加が観測されるかもしれません。
また昨年は、通常の極大よりも半日ほど遅れて、予想外に流星数が増加するのが観察されました。古い塵の影響だと推測されていますが、今年もこのような現象が観察されるかどうか、注目されます。このように予測できない現象が時折見られますので、注意が必要です。
国立天文台では、夏休みの時期で多くの人に見てもらいやすいこのペルセウス座流星群について、キャンペーンを行う予定です。日程など詳しいことは、決まり次第お知らせいたします。
三大流星群のひとつです。毎年ほぼ一定して、多くの流星が見られるという点では、年間最大の流星群と言えるでしょう。条件の良いときに熟練の観測者が観測すると、1時間に100個程度の流星を数えることは珍しくありません。
ふたご座流星群は、12月の上旬から流星が流れ始めると言われています。12月中旬に入って数が増加しますが、極大を過ぎると急に流星数が減る傾向にあります。
極大は諸説あるのですが、2009年の場合は12月14日9時〜16時頃と、残念ながら日本の昼間にあたります。
ふたご座にある放射点は、ほぼ一晩中夜空で見えていますので、夕方から明け方まで流れ星を見るチャンスがあります。ただし、夕方の早い時間帯は放射点が低いので、本格的に流れるのは、およそ21時以降となるでしょう。深夜の2時頃には、放射点がほぼ天頂に位置するため、流れ星が真上から降ってくるように見られます。
極大を考慮すると、12月13日深夜〜14日明け方や、14日21時〜深夜頃が観察におすすめの時間帯でしょう。
極大期は、新月(12月15日)の直前であり、一晩中月明かりの影響を受けずにすみます。大変好条件で観測できるでしょう。
母天体は、フェートン(Phaethon ファエトンとも呼ばれる)という名前の小惑星番号 3200 番の小惑星だと言われています。つまり、ふたご座流星群の流れ星の元になる塵(ダスト)の由来が、この小惑星であることになり、非常に古くには彗星として塵を放出していて、その後彗星活動を停止して小惑星になったとも推測されています。しかし、まだその確証はとれていないのが現状です。
このため、今観測されている流星のもとの塵が放出された時期がわからず、ダスト・トレイルによる流星群の予報などは、まだ行われていません。
国立天文台では、月明かりの影響がなく好条件で観測できる、このふたご座流星群について、キャンペーンを行う予定です。日程など詳しいことは、決まり次第お知らせいたします。世界天文年のしめくくりの天文現象として、ぜひ観察してみてはいかがでしょうか。