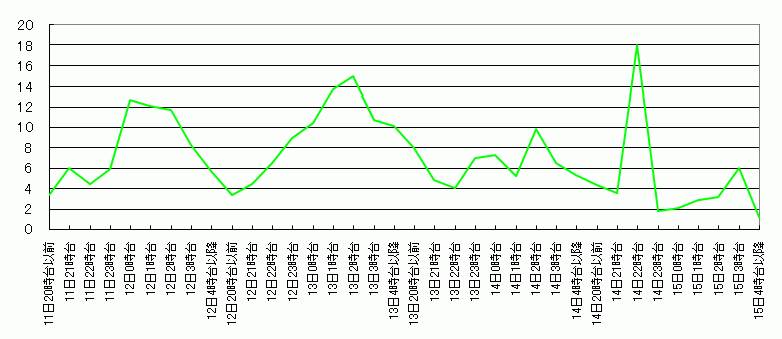
グラフのデータ
観察日時ごとに、観察された流星の数を、1時間あたりの流星数におおまかに換算してグラフにしました。
12日から13日にかけての真夜中過ぎに、最も多くの流星が観察されたようです。前日の晩(11日から12日にかけて)も多くの流星が観察されたようですが、翌日の晩(14日から15日にかけて)以降は流星の観察数が減っています。(14日の22時台に流星数が急に多くなったように見えますが、報告数は少ないために少数の極端なデータが強調されただけで、実際に流星の出現が活発だったわけではないと思われます。)
※ 正確な流星の個数・観察時間・雲の量・空の暗さなどはご報告いただいておりませんし、流星の出現数は放射点の高度によっても違います。また、12日から13日にかけて以外の日は報告数自体も少ないため、ここで算出した流星数や変動の傾向が、現実をそのまま表しているかどうかは確かではありません。、あくまで目安とお考えください。
日本流星研究会の速報によると、11日夜から12日明け方にかけては1時間あたり40〜50個程度、12日夜から13日明け方にかけては1時間あたり30〜60個程度のペルセウス座流星群の流星が観測されたようです。良い条件のものだけを集計しているため、みなさんからご報告いただいた流星数のおよそ4倍になっていますが、13日の2時頃に最も多く見られたところなどは、傾向が似ているようでした。
また、IMO(国際流星機構:英文)の速報によると、13日の11時(日本時間)前後に、予測されていた極大とは別の突発的な流星の出現があったようです。日本ではもちろん昼間のため流星は観察できなかったのですが、もし日本の夜にあたったら、予想以上に多くの流星が観察できたかもしれませんね。
※ 「群流星だけを観察した」報告をピックアップし、「天候が悪い」を外して集計しました。例えば、流星数は「3〜5個」を「4個」、観察時間は「11〜20分」を「15分」などとして計算をおこないました。