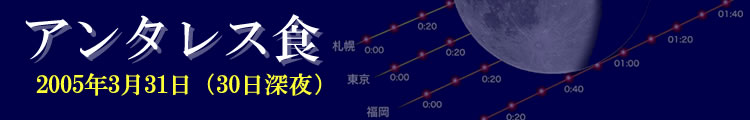
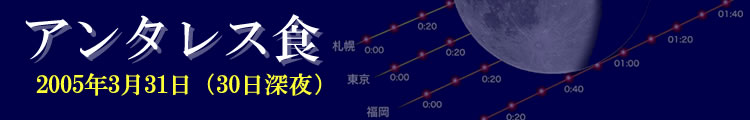
2005年3月30日の深夜(日付としては31日)、さそり座の1等星アンタレスが月の向こう側に隠される「アンタレス食」という現象が起こります。アンタレス食を条件よく(夜間に比較的高い位置で)観察できるのは、1991年以来実に14年ぶりのことです。また、1等星の食が次に日本で条件よく見られるのは2016年のアルデバラン食まで機会がありません。
そこで国立天文台では、このアンタレス食をターゲットにして「アンタレス食を計ろう」キャンペーンをおこなうことにしました。アンタレスが月に隠された瞬間の時刻と月の向こう側から出てきた瞬間の時刻を計って、報告ページから国立天文台に報告してください。携帯電話からの参加もお待ちしています。
遅い時刻に起こる現象ですが、春休み中でもありますので、お子さんも一緒に楽しんでみてください。
キャンペーン結果を公開しました。ご覧下さい。
→キャンペーン結果
携帯電話用のキャンペーンページへは、 http://www.nao.ac.jp/i/ からアクセスしてください。
月は、星座を形作る星々の間を移動し、平均27日余りでひとまわりしています。移動している月の通り道にちょうど星があれば、その星は月の向こう側に隠されることになります。このような現象を「食」(あるいは「星食」)と言います。
月が星々の間を通っていく道(「白道」と言います)は太陽の通り道(「黄道」と言います)に対して約5度傾いています。太陽はほぼ一定の通り道を通るのですが、月は運動が複雑なため、月の通り道はそのたびごとに違います。毎月同じ星が月に隠されるわけではないのは、このためです。
星が月に隠されることを「潜入」、星が月の向こう側から出てくることを「出現」と言います。月が星に近づいていく様子や、月が星から離れていく様子を観察すると、星空に対して月が意外と早く動いていることが実感できると思います。
暗い星まで含めれば食は頻繁に起こっていますが、1等星に限ると、黄道の近くに位置しているしし座のレグルス、おとめ座のスピカ、おうし座のアルデバラン、そして今回食が起こるさそり座のアンタレスの4つだけに食が起こる可能性があります。
今回のアンタレス食は、31日の0時台から1時台にかけて、日本全国(沖縄の南西部を除く)で観察できます。(31日の0時台ということは、30日の夜の現象であることに注意してください。くれぐれも翌日になってから気づかないように・・・。)
月は、南東の空の低い位置に見えているはずです。晴れていれば、月を見つけるのに苦労することはないでしょう。
ただ、月の見える方角に高い建物や山などがあると、月が隠されてしまって見えません。地平線近くまで見通せる場所で観察してください。
各地での潜入・出現時刻と、そのときの月の高度・方位は次の通りです。(高度は地平線から上方に,方位は北から東回りに測った角度です。)
ただし、この表の時刻はあくまで目安と考えてください。(例えば「札幌」といっても広いですので)場所が違えば時刻も違います。自分が観察する場所での潜入・出現時刻が、必ずしも正確にこの表の時刻どおりになるとは限らないことに注意してください。
| 場所 | 潜入 | 出現 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 高度 | 方位 | 時刻 | 高度 | 方位 | |
| 札幌 | 0時33分44秒 | 9度 | 140度 | 1時44分42秒 | 16度 | 155度 |
| 東京 | 0時29分09秒 | 14度 | 137度 | 1時40分28秒 | 22度 | 152度 |
| 福岡 | 0時26分54秒 | 9度 | 130度 | 1時23分08秒 | 17度 | 140度 |
| 那覇 | 0時51分28秒 | 16度 | 131度 | (接食) | ||
食が起こるときの月齢は20.3です。月の形は、満月から下弦(半月)に向かって小さくなりつつあります。
アンタレスは月の明るい側(「明縁」と呼びます)から潜入し、月の暗い側(「暗縁」と呼びます)から出現します。月は星と比べてたいへん明るく、特に今回は月が半月より大きいですので、潜入直前のアンタレスを肉眼で捉えるのは難しいかもしれません。
今回の食は、沖縄県那覇市あたりから南西の地域では見ることができません。しかし、那覇市と知念村を結んだあたりの地域では、月の縁がアンタレスぎりぎりに接近する「接食」という現象を観察することができます。月の縁にはクレーターや山などの地形による凹凸がありますので、場所によってはアンタレスが何回か明滅するのを見ることができるかもしれません。(珍しい現象ですので、観察した方は是非感想に書いて報告してください。)
食の時刻を知ることによってなにがわかるのでしょうか。
観察をした場所の正確な位置と、その場所で測定した正確な潜入・出現の時刻からは、星座を形作る星(恒星)と月との間の位置関係がわかります。恒星の位置や運動は、最近では欧州宇宙機構の位置天文衛星ヒッパルコスが精密な観測をしていますが、たくさんの星食を地上から精度よく観測することによって、ヒッパルコスの観測結果から誤差を取り除き精度を高めることができると期待されます。
また、星食を多くの場所で観察すると、月縁の地形を精度よく決めることができます。月面の地形はアメリカの探査機クレメンタインも月の周回軌道から観測をおこないましたが、星食の観測ではさらに精度のよい月縁の地形を知ることができます。
今回のキャンペーンでは、本格的な観測を目指すわけではありませんので、場所としては都道府県を、潜入・出現時刻は1秒単位で報告していただきます。この精度では上記のような成果は期待できませんが、それでも、皆さんの報告を集計することで、アンタレスの手前を月が移動していく様子がわかるかもしれません。
もし今回のキャンペーンをきっかけに星食に興味を持った方は、「関連情報」などを参考に、本格的な観測を目指してください。
身の回りで比較的簡単に、ある程度正確な時刻を手に入れる方法のひとつとして、電波時計があります。情報通信研究機構が発信している標準電波を受信して、時刻を修正するしくみを持った時計です。ただ、受信した電波を元に、ずっと時刻を修正し続けているわけではないようですので、観察の直前に電波の情報に合わせて時刻を修正するのがよいでしょう。(ただし、電波時計は時刻を修正した直後でも0.3秒程度の誤差はありえますので、本格的な時刻測定には不向きです。)
また、電話でNTTが提供している「117番」の時報サービスも利用できます。携帯電話は情報が伝わる途中での時間の遅れが大きいため、携帯電話よりも固定電話のほうが精度がよいようです。
本格的な観測では1秒以下の精度が重要になりますが、今回のキャンペーンでは、あまり精度にこだわらず、実際に自分で測定をするときの難しさや楽しさを体験してください。
月が半月より大きく明るいため、肉眼での観察は難しいかもしれません。特に、潜入は明縁で起こりますので、月の明るさに邪魔されてしまい、アンタレスが月に近づくにつれて、アンタレスが見えているのかいないのかわからなくなってしまう可能性があります。
暗縁で起こる出現は、月の明るい部分がアンタレスのすぐそばにあるわけではありませんので、潜入に比べると観察がしやすいはずです。
難しいかもしれませんが、双眼鏡や望遠鏡を持っていない方は、どこまで肉眼で観察が可能なのかに挑戦してみてください。
双眼鏡を持っている方は、双眼鏡を使ってアンタレス食に挑戦してください。
双眼鏡を、できるだけ三脚などに固定して見るようにしてください。双眼鏡を手に持っていると、どうしても揺れてしまい、あまりよく見えません。
望遠鏡を持っている方は、望遠鏡を使ってアンタレス食を見てみましょう。
口径5〜6cm程度の望遠鏡でも、十分にアンタレス食を楽しむことができるはずです。
倍率は、アンタレスがよく見えるよう調整してみてください。ただ、あまり倍率を高くしてしまうと、出現の位置が望遠鏡の視野に入っていないために、気づかないうちに出現してしまっているということにもなりかねませんので、注意してください。
また、望遠鏡の倍率が高い場合には、月とアンタレスが日周運動のために結構早く動いていきますので、追尾する必要があるかもしれません。前もって月や星を観察して、想定した倍率の視野の中で、月や星がどのくらいの速さで移動するのかを知っておくとよいかもしれません。
ズームや望遠レンズなどが使えて、ある程度拡大撮影ができるカメラであれば、露出を調整することによって、月とアンタレスが接近した様子を撮影することができます。月面に露出を合わせるのがよいでしょう。月が露出オーバーになってアンタレスが埋もれてしまわないように注意しましょう。暗縁からの出現では、出現からあまり時間がたっていないときでも、月の明るい部分とアンタレスはある程度離れていますので、月の明るさにあまり邪魔されずにアンタレスを撮影できるでしょう。
カメラがぶれないよう、できるだけ三脚で固定するようにしましょう。
ビデオカメラの場合にも、ある程度拡大ができ、暗いものを写すことができるものであれば、月とアンタレスの位置関係が変化していく様子を撮影することができるかもしれません。ビデオカメラを持っている方は挑戦してみてください。