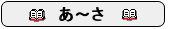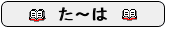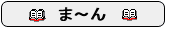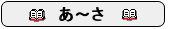
 ガバナー式 ガバナー式
- 重りを利用して天体追尾を行う重錘式時計駆動式の望遠鏡。第一赤道儀室の望遠鏡はこの方式で作られている。
 干渉計(かんしょうけい) 干渉計(かんしょうけい)
- 一般に「波」を干渉させる装置全般のことを干渉計という。天体観測装置としては、複数の(光学、電波)望遠鏡を連動させて測量したり、非常に細かな天体の画像を合成する装置のこと。電波望遠鏡では、たくさんの電波望遠鏡を組み合わせ、それぞれのアンテナで受信した電波を互いに干渉させることにより、配置した望遠鏡群の広がりと同じ口径の電波望遠鏡と同等の分解能を得ることができる。
 銀河(ぎんが) 銀河(ぎんが)
- 恒星や星間物質等の巨大な集団。私たちの太陽系は、天の川銀河の中にある。
 屈折式望遠鏡(くっせつぼうえんきょう) 屈折式望遠鏡(くっせつぼうえんきょう)
- 天体望遠鏡の形式の1つで、凸レンズ(対物レンズ)を利用して光を集め、接眼レンズで像を拡大させるタイプの望遠鏡。
 恒星(こうせい) 恒星(こうせい)
- 太陽のように自分で光を発せられる星。
 光年(こうねん) 光年(こうねん)
- 光が1年間に進む距離で、約9兆5000億キロメートル。
 黒点(こくてん) 黒点(こくてん)
- 太陽の表面上に見える黒い斑点状のもの。この部分は、まわりの温度よりも低く、光球表面温度が絶対温度で約6000度あるのに対し、約4000度〜4500度程度である。
 子午環(しごかん) 子午環(しごかん)
- 太陽系天体や12等級までの星の天球上の絶対位置を決定する。天文座標は子午環観測によって構築されている。
 重力波(じゅうりょくは) 重力波(じゅうりょくは)
- アインシュタインの一般相対性理論によれば、物体の周囲の空間はゆがんでいて、この物質が運動すると、そのゆがみが変化し、波となって伝わる。これを重力波という。重力波を捕らえることにより、超新星爆発やブラックホールの形成など、強い重力場での現象を調べることができる。
 星間物質(せいかんぶっしつ) 星間物質(せいかんぶっしつ)
- 目には見えないが、星と星との間には様々な物質がある。これらを星間物質とよぶ。
 赤道儀望遠鏡(せきどうぎぼうえんきょう) 赤道儀望遠鏡(せきどうぎぼうえんきょう)
- 日周運動にあわせて(たとえば天の赤道にそって)望遠鏡を動かすことができる望遠鏡。
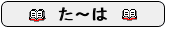
 電波望遠鏡(でんぱぼうえんきょう) 電波望遠鏡(でんぱぼうえんきょう)
- 宇宙には、可視光だけではなく、γ線やX線等,さまざまな波長の電磁波が発せられている。これらの電波を観測するのが、電波望遠鏡である。
 反射式望遠鏡(はんしゃしきぼうえんきょう) 反射式望遠鏡(はんしゃしきぼうえんきょう)
- 天体望遠鏡の形式の1つで、光が一点に集まるように磨いた反射凹面鏡(主鏡)によって、像を拡大させる望遠鏡。
 VLBI(ぶいえるびーあい) VLBI(ぶいえるびーあい)
- Very Long Baseline Interferometry(超長基線電波干渉計)の頭文字をとったもの。
離れた場所に設置した複数の電波望遠鏡を使って同時に観測すると、離れた距離の分だけ、分解能が高くなる。そのため、天体をより詳しく調べることが可能になる。
 ブラックホール ブラックホール
- 強力な重力のために光さえも吸い込む天体のこと。
 フレア フレア
- 太陽面上の一部分で、突発的に多量のエネルギーが放出される爆発現象。
 分解能(ぶんかいのう) 分解能(ぶんかいのう)
- どのくらい細かいところまで見分けることができるかを示すもので、望遠鏡では秒で表す。数値が小さいほど、よく見える。例えば、口径10cmの望遠鏡では、1.16秒である。
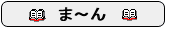
 ミリ波・サブミリ波 ミリ波・サブミリ波
- 電波の中で、波長がミリメートル程度のものをミリ波、ミリメートル以下のものをサブミリ波と言いう。
 メシエ(M) メシエ(M)
- 星雲・星団のリストを作った天文学者シャルル・メシエの名前からつけられている。メシエの作ったカタログには、天体にM1から110まで番号がふられていて、例えば、「かに星雲」はM1、「オリオン大星雲」はM42とつけられている。
|