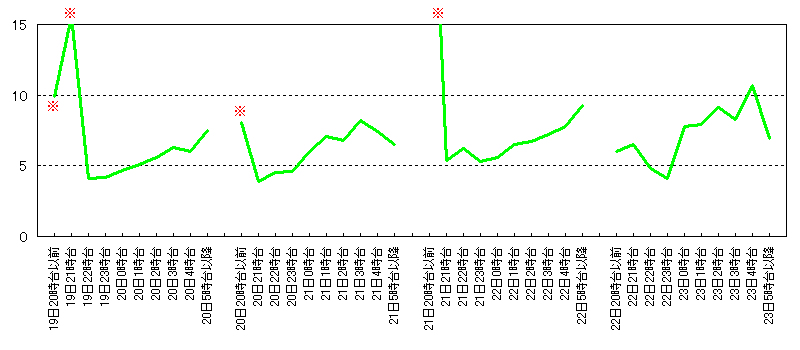
「見えるかな?オリオン座流星群」キャンペーンでは、1万4千件を超える観察報告をいただき、ありがとうございました。通常のキャンペーンよりも、データの数が大変多いため、集計に時間がかかることが予想されます。
そこで「1時間あたりの流星数」について、現在の暫定値を使用して、速報的に解説いたします。
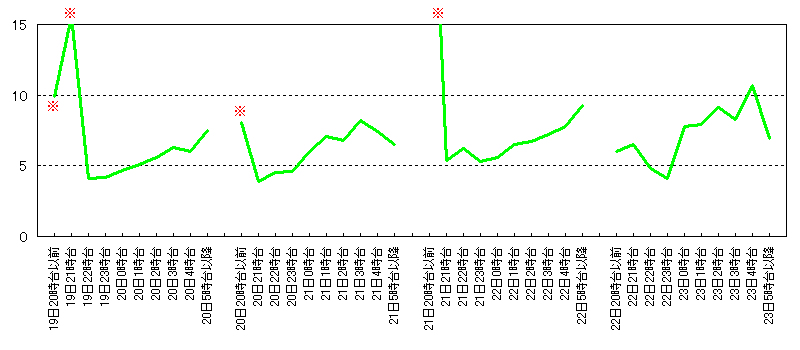
まず、20時台以前や21時台で、グラフが突出した部分が見受けられました(グラフの「※」の部分)。これらは、報告数が大変少ない時間帯のため、集計された値の誤差が大きくなります。したがって、これらの突出部分で、必ずしも出現数が多かったわけではない、と思われます。
これらの部分を除くと、19日夜〜23日朝にかけて、おおむね1時間あたり5個〜10個程度の流星を観察することができたようです。
キャンペーンでは、市街地で星が見づらい地域の観察結果も含めて、報告をいただいております。これまでのキャンペーンでは、この観察結果の値は、空の暗い条件のよい場所での観察と比較するとおよそ4分の1〜5分の1となっていました。このことを考慮すると、空の暗いところでは、およそ1時間あたり20〜50個程度の出現だったのではないかと、推測することができます。これは、ほぼ予想された出現数でした。
また流星が突出して多く観察された日はなく、どの日もほぼ同じくらいの流星が観察されています。
今回のオリオン座流星群では、極大(最も多く流星が流れて活発となる時期)の正確な予想が難しい状況でした。結果からは、はっきりとした極大は観察されませんでした。キャンペーン期間を通して、ある程度活発な出現が継続した模様です。
時間帯に注目すると、どの夜もおおむね明け方に向かって、流星が増加していったようです。オリオン座流星群の放射点は、明け方に向けて空の高い位置上っていき、4時台に最も高くなって観察条件が良くなります。この効果により、明け方に向けて流星数が増えていったからだと考えられます。
IMO(国際流星機構)の集計では、10月20〜24日(世界時)で、オリオン座流星群が活発でした。「ZHR」という理想的な条件で観測した場合の1時間あたり流星数を表す値では、この期間に30〜50の間で増減を繰り返していた模様です。2005年以前のオリオン座流星群は、ZHRの値の最大が30でしたから、この数日間はずっと活発な状況が続いたことになります。また、期間中、ほぼ同じくらいの数が観察されたキャンペーンの観察結果ともよく合っているようです。
日本流星研究会の速報集計では、このZHRの値が、19〜20日の夜で31、20〜21の夜で39、21〜22の夜で55となっています。22日の夜以降の集計値はまだ掲載されていませんが(10月27日現在)、キャンペーンが始まった19〜20日の夜には、すでにオリオン座流星群が活発化していたことを示しています。
今回のオリオン座流星群では、むらのある出現が見られました。国立天文台メンバーの観察では、オリオン座流星群の流星が多く流れる時間帯が10〜20分程度続いた後、その後しばらく流星が見られない時間帯が続く、ということが繰り返されているように感じられました。このようなことは、他の観測者からも指摘されているようです。
したがって、流星があまり流れていない時間帯に運悪く当たってしまった場合には、ほとんど流星が流れていない、と感じられた方も多かったかもしれません。今回のキャンペーンでは、15分以上の観察を呼び掛けておりましたが、確実に流星を見るためには、もう少し長い時間の観察が必要だったかもしれません。