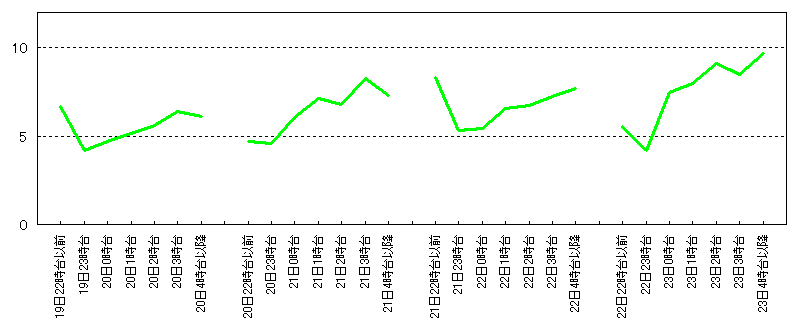
グラフのデータ
観察日時ごとに、観察された流星の数を、1時間あたりの流星数におおまかに換算してグラフにしました。
キャンペーン期間中を通じて、おおむね1時間あたり4〜10個程度の流星を観察することができたようです。
各夜毎の1時間あたりの流星数は、19〜20日で4〜6個、20〜21日で4〜8個、21〜22日で5〜8個、22〜23日で4〜10個となりました。22〜23日の夜が若干多めで、19〜20日の夜が若干少なめだったようです。
キャンペーンでは、市街地で星が見づらい地域の観察結果も含めて、報告をいただいております。これまでのキャンペーンでは、この観察結果の値は、空の暗い条件のよい場所での観察と比較するとおよそ4分の1〜5分の1となっていました。このことを考慮すると、空が暗く観察条件の良い場所では、およそ1時間あたり15〜50個程度、流星が見られたのではないかと、推測することができます。この値は、ほぼ予想された出現数と言えるでしょう。
なお今回、流星が突出して多く観察された日はありませんでした。キャンペーン期間を通して、ある程度活発な出現が継続した模様です。今回のオリオン座流星群では、極大(最も多く流星が流れて活発となる時期)の正確な予想が難しい状況でしたが、観察結果からは、はっきりとした極大はわかりませんでした。
ただ、キャンペーン最終夜となる22〜23日、2時台〜4時台以降で1時間あたり9個前後と、少々多めに観察されたようです。日本流星研究会(後述)でも、やはり22〜23日に最も活発となった様子が報告されています。以前から言われている極大よりも約1日遅く、興味深い結果と言えるでしょう。
時間帯に注目すると、多少の増減は見られますが、どの夜もおおむね明け方に向かって流星数が増加していったようです。オリオン座流星群の放射点は、明け方に向けて空の高い位置上っていき、4時台に最も高くなって観察条件が良くなります。この効果により、明け方に向けて流星数が増えていったからだと考えられます。
※ 正確な流星の個数・観察時間・雲の量・空の暗さなどはご報告いただいておりませんし、流星の出現数は放射点の高度によっても違います。その他にもいろいろ不確定な要素がありますので、ここで算出した流星数や変動の傾向が、現実をそのまま表しているかどうかは確かではありません。ご了承ください。
※ キャンペーン期間中に掲載した速報集計のグラフでは、観察報告の少ない時間帯で流星数が突出して多いという結果となっていました。これは、観察数が少ないことで誤差が大きくなり、これが反映してしまったものと考えられます。
日本流星研究会の速報集計では、「ZHR」という理想的な条件で観測した場合の1時間あたり流星数を表す値が、19〜20日の夜で約35、20〜21の夜で約39、21〜22の夜で約55、22〜23の夜で約61となっています(10月28日現在の集計)。
最も多く観察されたのは22〜23日の夜で、前日の21〜22日の夜もかなり多くの流星数が観察されていて、この2日間に極大があった模様です。
キャンペーンが始まった19〜20日の夜に、すでにオリオン座流星群が活発化していたこと、また22〜23日夜に最も多く見られたことなどは、キャンペーンの結果と似た傾向を示しているようです。
なお、今回キャンペーンは23日まででしたが、24〜25日の夜もZHRが約35と、まだ活発だった様子がうかがえます。
IMO(国際流星機構)の集計では、10月20〜24日(世界時)で、オリオン座流星群が活発でした。「ZHR」の値は、この期間に30〜50の間で増減を繰り返していた模様です(10月28日現在の集計)。2005年以前のオリオン座流星群は、ZHRの値の最大が30でしたから、この数日間はずっと活発な状況が続いたことになります。
ただし、日本流星研究会の結果と比較すると、極大は、あまりはっきりしなかったようです。
キャンペーン期間中を通じて、オリオン座流星群が活発な期間の中にあったということは言えるでしょう。
今回のオリオン座流星群では、その出現に「むら」がある様子が観察されました。国立天文台のメンバーによる観察では、オリオン座流星群の流星が多く流れる時間帯が10〜20分程度続いた後、その後しばらく流星が見られない時間帯が続く、ということが繰り返されているように感じられました。つまり、流星が多い時間帯と、少ない時間帯があったことになります。このようなことは、他の観測者からも指摘されているようです。
したがって、流星があまり流れていない時間帯に運悪く当たってしまった場合には、ほとんど流星が流れていない、と感じられた方も多かったかもしれません。今回のキャンペーンでは、15分以上の観察を呼び掛けておりましたが、確実に流星を見るためには、もう少し長い時間の観察が必要だったかもしれません。