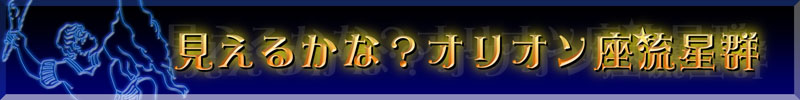
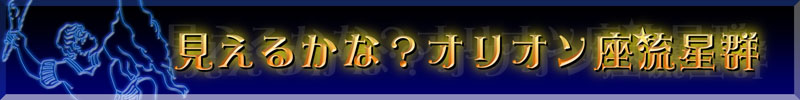
2006年から2010年にかけて、オリオン座流星群の活動が活発となることが期待されています。この理由について解説します。
オリオン座流星群は、観測条件が揃ったときでも1時間に20個程度しか見られない中規模な流星群です。しかし、2006年に突然流星数が増加しました。このことは、誰からも予想されていなかったため、観測者を大変驚かせました。
この年、IMO(世界流星機構)の調べでは、ZHRという値(理想的な空の下で観測した場合の1時間あたりの流星数)は、50以上を記録しました。日本の熟練観測者の中には、1時間に100個以上の流星を数えた人も出る程でした。ペルセウス座流星群などの「三大流星群」と呼ばれる流星群と同じ程度か、それを上回るほどの活発な出現で、オリオン座流星群としては過去最大級の規模の出現でした。
2006年の観測結果をふまえて、国立天文台の佐藤幹哉広報普及員と渡部潤一准教授は、オリオン座流星群のチリの粒のチューブ状の流れ(ダスト・トレイルと呼ばれる)の計算に取り組みました。オリオン座流星群の元となるチリの粒を放出している天体(母天体)は、あの有名なハレー彗星(1P/Halley)です。
現在計算されている最も古いハレー彗星の軌道(紀元前1404年)までさかのぼり、ハレー彗星からチリの粒を放出させて、その分布を計算しました。すると、およそ3000年前にあたる紀元前1266年、紀元前1198年、紀元前911年に、それぞれハレー彗星から放出されたチリの粒の流れが、2006年から2010年にかけて、地球軌道に接近していることがわかりました。
図は、このチリの粒の流れを、地球の軌道平面で切断した場合の断面図です。2006年〜2010年(図の右側)には、多くのチリの粒の流れが地球軌道と交差していることがわかります。
実際、2007年には2006年と同じくらいでZHRが50〜70程度の出現が観測されました。また、2008年は若干少なくなりましたが、それでもZHRで30〜40程度と、2006年以前の例年(多い年でもZHRは最大で30程度)よりは多く見られました。したがって、今年2009年も、オリオン座流星群の活発な活動が期待されるのです。
流星群の元となるチリの粒も、母天体のハレー彗星と同様、太陽のまわりを回っています。2006年から2010年にかけて地球軌道と接近しているチリの粒について、その公転周期を計算すると、ハレー彗星の約76年よりも短い約71年であることがわかりました。この公転周期は、木星の公転周期(11.86年)の6倍に相当し、木星の重力の影響を強く受けて、地球に接近する軌道が保たれてきたと推測されています。
したがって、このようなチリの粒と地球が遭遇するチャンスはおよそ70年に1度の数年間に限られることになります。実際、約70年前にあたる1936年には、オリオン座流星群が活発化したという記録が残っています。今回のチャンスは来年2010年までと計算されており、2011年以降は2006年以前と同じ程度に流星数が少なくなってしまうと予想されます。今年2009年と来年2010年がラストチャンスなのです。
流星群が最も活発に活動する、すなわち最も多く流星が流れる時期を「極大」と呼びます。活発な流星群では、この極大と呼ばれるような期間は、数時間から1日程度しか続きません。それを過ぎると半分から数分の1程度に減ってしまいます。
しかしオリオン座流星群が活発になった2006年は、この活発な期間が約4日間も続きました。計算によれば、チリの粒の放出された年代が違うため、その範囲が少し広がっていて、地球がその部分を通過するのに時間がかかるためだと推測されます。
近年のさまざまな研究成果により、チリの粒が放出されてから数百年以内の場合は、完全では無いものの、流星群の活動状況について詳しく予報をすることが可能になってきました。しかし、今回のオリオン座流星群のように3000年も経過していると、色々な誤差が大きくなり、残念ながら予報を詳しく行うことは難しい状況です。
2009年の出現数は、2007年と似ていると考えられます。2007年はZHRの値で50〜70でしたが、今年は40〜50程度ではないかと考えられます。実際に見られる流星の数は、天の川が見えるような条件の良いところで、1時間に30〜40個程度となります。市街地のような空が明るいところでは、この半分〜数分の1となるでしょう。
これは、あくまでも目安であり、実際にはもっと多いかもしれませんし、逆に少ないかもしれません。実際に観察してみないとわからないのです。
流星群が最も活発になる極大を正確に予想するのも難しい状況です。計算上、チリの粒の流れと地球が最も近づくのは、10月19日頃です。しかし近年の状況では、10月21日前後にも流星が多く見られています。したがって、10月19日頃から23日頃まで、場合によると25日くらいまで、注意して観察する必要があります。
今回のキャンペーンでは、10月19日夜から10月22日夜(23日朝)までの期間で、観察を呼びかけています。この期間の中でいつ流星群が最も活発になるか、ぜひ注目して観察してください。キャンペーンでは、1時間あたりの流星数をリアルタイムに集計する予定です。この集計から、最も活発になったのがいつだったのかわかるかもしれませんので、多くの方にぜひご参加いただきたいと思います。