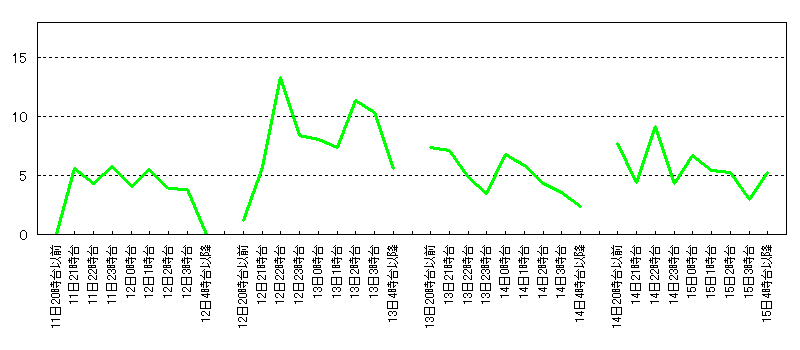
グラフのデータ
観察日時ごとに、観察された流星の数を、1時間あたりの流星数におおまかに換算してグラフにしました。
今回のキャンペーンでは、8月12日夜から13日朝にかけて、流星数が多かった様子がわかりました。最も多かったのは、12日の22時台という結果になりました。また13日の2時台と3時台にも、流星数が多かった様子をうかがい知ることができます。
12日夜〜13日朝と比較して、その前後の3夜は、流星数がおよそ半分程度になったようです。14日夜〜15日朝は、もう少し流星数が減ってしまうかと思いましたが、前夜の13日夜〜14日朝と同じかむしろやや多い傾向が見られました。前夜よりも天気が良く、多く流星を見ることができたのかもしれません。
※ 正確な流星の個数・観察時間・雲の量・空の暗さなどはご報告いただいておりませんし、流星の出現数は放射点の高度によっても違います。その他にもいろいろ不確定な要素がありますので、ここで算出した流星数や変動の傾向が、現実をそのまま表しているかどうかは確かではありません。
日本流星研究会の速報集計によると、今年のペルセウス座流星群が最も多く観測されたのは、13日2時台から3時台で、1時間あたり約40〜60個の流星が観測されています。今回のキャンペーンでは、このおよそ5分の1の値となっています。キャンペーンでは、空が明るい市街地で場所で観察した人もいれば、きれいな暗い空で観察した人もいます。また流星観察の初心者の人もいれば、経験者の人もいます。キャンペーンの集計値は、このようなさまざまな条件を区別無く集計した値となっています。一方で、日本流星研究会では、空の暗い観測条件の良い場所での観測のみが集計され、またそのほとんどがベテランの観測者によるものです。このため、キャンペーンの方が、見える流星の数は少なくなります。過去のこれまでの集計では、キャンペーンの値は、日本流星研究会の値の4分の1から5分の1程度となる傾向にあり、今回も同様でした。
※本キャンペーンの値では、12日22時台に一つの山が観測されています。日本流星研究会の結果では、本キャンペーンの数値に相当する1時間あたり流星数(HR)についてはこのピークが出ていませんが、色々な条件を加味して算出する修正された流星数(ZHR)では、22時台に少し多いという結果が出ています。キャンペーンの結果と関係するかどうかはわかりませんが、興味深い結果でした。
IMO(国際流星機構:英文)の報告によると、今回のキャンペーンでも流星が多く見られた8月13日3時頃に、極大のひとつが観測されています。
このほかに、8月12日の17時頃と8月13日の15時頃にも極大が観測され、世界的には3つの極大が観測されたようでした。2つの極大は、日本では昼間にあたり流星が観測できない時間帯でした。
※ 時刻はすべて日本時間です。
※ 「群流星だけを観察した」報告をピックアップし、「天候が悪い」を外して集計しました。例えば、流星数は「3〜5個」を「4個」、観察時間は「11〜20分」を「15分」などとして計算を行いました。