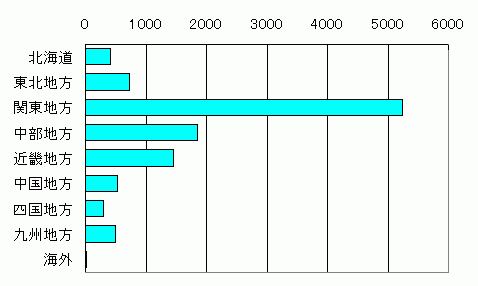
グラフのデータ
このページでは、2007年8月におこなった「夏の夜・流れ星を数えよう」キャンペーン(ペルセウス座流星群)の結果をご報告します。
全部で11375件(うち有効11014件)というたくさんの観察結果のご報告をいただきました。今回の報告件数は、これまでの9回のキャンペーンをはるかにしのぐ件数となりました。(これまで一番多かった報告件数は、2005年1月におこなった「マックホルツ彗星見えるかな?」キャンペーンの2724件。)キャンペーンへのご参加ありがとうございました。
今回、九州地方・四国地方・近畿地方などのわずかな地域を除き、ほとんどの地域でキャンペーン期間中にわたって天候に恵まれたことが、多くの皆さんにご参加いただけたいちばんの要因ではないかと考えています。
都道府県別の報告数です。
都道府県名をクリックすると、その都道府県の(簡易)集計結果をご覧いただけます。
北海道:408 青森県:97 岩手県:69 宮城県:116 秋田県:129 山形県:136 福島県:180 茨城県:400
栃木県:243 群馬県:124 埼玉県:899 千葉県:971 東京都:1514 神奈川県:1084 新潟県:243 富山県:154
石川県:116 福井県:97 山梨県:119 長野県:311 岐阜県:130 静岡県:282 愛知県:394 三重県:89
滋賀県:102 京都府:165 大阪府:426 兵庫県:428 奈良県:148 和歌山県:97 鳥取県:48 島根県:64
岡山県:146 広島県:179 山口県:89 徳島県:77 香川県:102 愛媛県:104 高知県:18 福岡県:205
佐賀県:32 長崎県:48 熊本県:81 大分県:57 宮崎県:20 鹿児島県:30 沖縄県:24 海外:19
地方別の報告数です。
特に関東地方からご報告をたいへん多くいただきました。
海外からも19件のご報告をいただいています。
観察日時別の報告数です。
流星の出現数が最も多くなるのではないかと予想されていた、13日の0時過ぎに観察なさった方がいちばん多くいらっしゃいました。
観察時間別の報告数です。
昨年12月のふたご座流星群のときにおこなったキャンペーンでは、「5分未満」と「30分以上」が同数で、他も大きくは違わなかったのですが、今回のキャンペーンでは、長い時間観察なさった方ほど多いという結果になりました。
見ることができた流星の個数ごとの報告数です。
多くの方が3個以上の流星を観察なさっています。(「見るまでやめられなかった」のかもしれませんね。)
全国的にお天気に恵まれたようですが、「天気が悪い」という方もわずかですがいらっしゃいました。また、お天気は悪くなかったのですが、残念ながら流星を見ることができなかったという方もいらっしゃいました。今回は残念でしたが、是非、次の流星群にもチャレンジしてください。
各地方での報告数を100%として、報告された流星の個数の割合を示しました。
近畿地方・四国地方・九州地方の一部でお天気が悪かったようです。
関東地方・近畿地方で流星の見える個数が少ないのは、大都市部が近くにある影響でしょうか。
流星を見た経験ごとに報告数を集計しました。
流星を見るのが今回初めての方もたくさんいらっしゃいましたが、多くの方は、これまでに何回も流星を見たことがある方でした。
参加者の年齢別に報告数を集計しました。
参加された方の多くは30才代・40才代の方でした。
夏休みでしたので、お子さんも多く参加されています。条件の良い真夜中過ぎはお子さんにはつらかったかもしれませんが、真夜中前でも流星をたくさん見ることができたという感想を多くいただきました。
観察日時ごとに、観察された流星の数を、1時間あたりの流星数におおまかに換算してグラフにしました。報告の選択肢が最大でも「11個以上」でしたので、実際に見ることができた流星の数はさらに多かったのではないかと思われます。
真夜中前よりは真夜中過ぎのほうが観察された流星の数が多く、12〜13日の晩と13〜14日の晩は、その前後の日に比べて観察された流星の数が多いように見えます。
ただし、「14日20時台以前」と「15日4時台以降」は報告数がたいへん少ないため、現実の傾向からは大きく外れた数値になっていると思われます。
(正確な流星の個数・観察時間・雲の量・空の暗さなどはご報告いただいておりませんので、ここで算出した流星数は正確な数字ではありませんし、どこまで現実の傾向を正しく表しているかもわかりません。あくまで目安とお考えください。)
IMO(国際流星機構)の速報では、今年は明確な極大がなく、13日4時〜14日6時(いずれも日本時間)の間で流星の出現が多く観測されたもようです。
参加された皆様からいただいた感想をご紹介します。全部ご紹介したいところですが、それではたいへんな量になってしまいますので、ここでは一部をピックアップしました。
流星を見ることができた方の感想です。
残念ながら流星を見ることができなかった方の感想です。
ペルセウス座流星群の流星には明るいものがありますので、空がそれほど暗くない場所でも、流星をご覧になれた方が多くいらっしゃったようです。都会でもあきらめずに、少し時間をかけて観察をしてみるとよいかもしれませんね。また、流星は極大の日にだけ現れるわけではありません。できれば一日だけでなく観察を続けると、流星を見ることができる機会が増えると思います。
星空は人を幸せにしてくれることがあるようです。
星空を見上げることは、いろいろなことを思うきっかけになるのでしょうか。
解説ページで、蚊に関する注意をお伝えしていなくて申し訳ありませんでした。
ここに取り上げるのは深刻な事例ではありませんが、夜間の行動では、事故やまわりへの迷惑には十分注意してください。
お書きいただいた感想などを拝見すると、多くの方が共通して疑問に思っていることがあるようです。いくつかの項目を簡単に解説しておきます。
ご報告の際に、観察時刻を間違った方が多くいらっしゃいました。
普段の生活では、真夜中を越え、朝になる前の日付を意識することは少ないと思いますが、天文現象を観察するときには注意が必要です。
例えば、13日の3時というと、つい、13日の夜から準備をすればよいように思ってしまうことがあります。しかし、じっくり考えるとわかりますように、13日の3時に観察をするためには、12日の夜から準備を始めないと間に合いません。
流星を観察していると、そのうちのいくつかは、尾を引いていたり、もやもやとしたものがあとに残るように見えます。この、あとに残る光を「痕(こん)」と言います。明るい流星では痕が顕著に残る場合があり、数秒から十数秒も残っていることもあります。
流星は、数ミリメートルから数センチメートル程度の塵粒が地球大気に飛び込み、80〜100キロメートルの上空で、大気との摩擦によって高温になると同時に発光する現象です。「隕石」とは、このような塵粒が大気で蒸発しきることなく、地表まで達したものを言います。
明るい流星を目にすると「隕石か?」と思ってしまいますが、ほとんどの流星は大気中で蒸発してしまい、地表に届くことはありません。隕石の落下はたいへん珍しく、数年に一度程度しか起こりません。
2001年のしし座流星群をご覧になった方は、ペルセウス座流星群をしし座流星群と比較して「ペルセウス座流星群はしし座流星群ほどではない」という感想をお持ちのようです。たしかに、2001年のしし座流星群は、(数十年から百年 に一度という)たいへん珍しい大出現でした。残念ながら、あのような流星の大出現を見る機会は、一生のうちに何度もあることではありません。
しかし、月の影響が少ない年であれば、空が十分に暗い場所で極大近くの晩に空を眺めた場合、ペルセウス座流星群は1時間に30個以上の出現を毎年見せてくれます。数十年に一度の派手な流星群もよいのですが、毎年のように多くの流星を見せてくれるペルセウス座流星群も結構楽しめるのではないでしょうか。
流星より遅い光が星空を移動していくのを見た方が多くいらっしゃいます。これは多くの場合、人工衛星です。
地上には太陽の光が当たっていないために暗いときでも、地球の上空を回る人工衛星には太陽の光が届き、その光が反射して、地上にいる私たちにはゆっくり移動する光の点として見えます。移動する速さは「飛行機ぐらい」ですが、飛行機と違って光はひとつで早い点滅はしませんし、もちろん音もしません。ゆっくりと明るさを変えながら、次第に暗くなって見えなくなってしまいます。多くの場合、数十秒から数分間見えています。
UFOを見たという方も何人かいらっしゃいましたが、多くの方は人工衛星をご覧になったのではないでしょうか。もちろん、人工衛星だということがわかるまではUFO(未確認飛行物体)ですが・・・。
また、立って空を見上げていると、無意識のうちに体が揺れていることがあります。観察が長時間におよぶとなおさらです。その状態で人工衛星や飛行機など、直線で移動するものを見ると、自分はじっとしているつもりでも体が揺れて、人工衛星や飛行機がフラフラと蛇行しているように見えます。
そんなときには、地面に寝転がったり、固定された物体(柱など)にもたれかかるなどして、体の揺れがない状態で観察し直してみてください。可能でしたら、三脚に固定した双眼鏡で観察したり、カメラをやはり三脚に固定して写真を撮ったりすれば、本当に蛇行しているかどうかを確認することができます。
それから、「鳥」も謎の飛行物体として観察されることがあります。
鳥は、夜は空を飛ばないと思われているようですが、そんなことはありません。双眼鏡などで夜空を眺めていると、鳥が飛ぶ姿を目撃することがあります。集団でV字型の編隊を組んでいることもあります。地上の光を受けているのか、光っているように見えることもあるようです。
流星群など天文現象に関する情報を知るにはどのようにすればよいか、とお書きになっている方もいらっしゃいました。
国立天文台では、今回のペルセウス座流星群のような天文現象や、宇宙や天文に関する最新情報を「アストロ・トピックス」というメールマガジンで発信しています。もし興味がありましたら、是非ご購読ください。購読の申込方法はこちらをご覧ください。
また、月々の天文現象などの情報は「ほしぞら情報」をご利用ください。
「テレフォン天文情報サービス」では音声による天文現象の案内を提供しています。